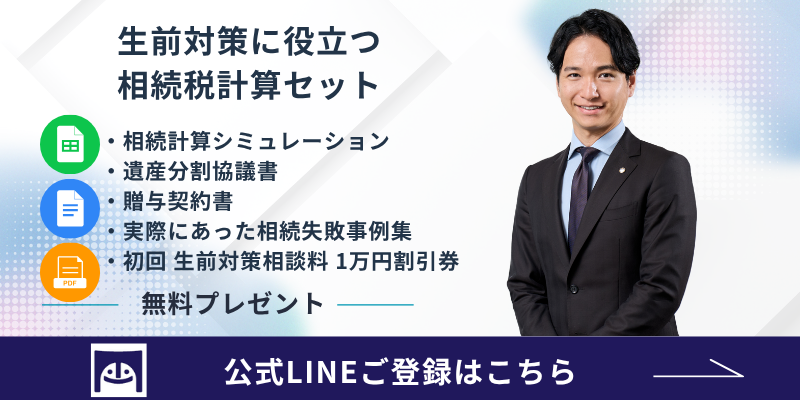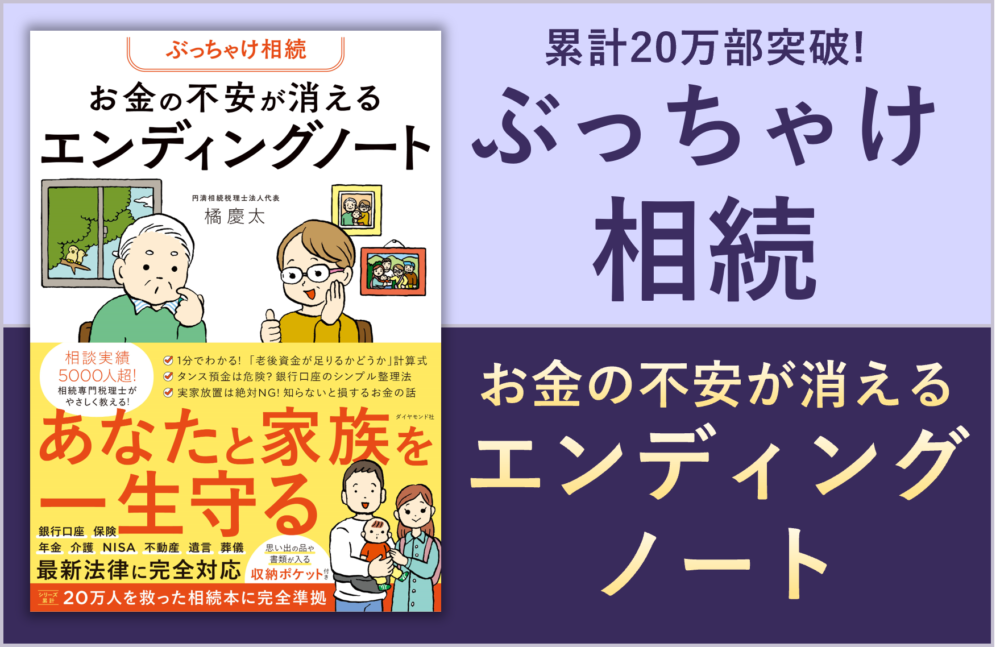円満相続税理士法人 税理士 大学在学中から税理士を目指し25歳で官報合格。 法人税務を経て現在は円満相続税理士法人にて、 相続・事業承継のプロとして、 申告・税務相談・執筆・セミナー講師など 幅広く活動中! 詳しいプロフィールはこちら
相続は人生の終着点というイメージが強く、被相続人=お年を召された方という印象が強いのではないでしょうか。
実際、弊社へご相談頂く大半のお客様はその通りなのですが、中には比較的若くしてお亡くなりになる方もいらっしゃいます。
若くしてお亡くなりになられた方は働き盛りの方も多く、このような方の相続においては、必ずと言っていいほど、死亡退職金・弔慰金の取扱いが論点になります。
死亡退職金・弔慰金の税務上の取扱いは注意点が想像以上に多いです。
一般的な取扱いと併せて、一歩踏み込んだポイントもおさえていきましょう!
【1】死亡退職金は死亡退職に限る!?
一般的に死亡退職とは、現役バリバリの時に何らかの理由で亡くなってしまい、遺族に死亡退職金が支払われるというケースが多いかと思います。(死亡=退職)
例えば、役を勤め上げ、退職した直後に、退職金の支給が確定しないまま、亡くなってしまったようなケースはどうなるのでしょうか。(退職→死亡)
(1)一般的な取扱い(死亡=退職)
まず、おさらいとして、被相続人の死亡により、遺族が、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金を受け取った場合、相続税の課税対象となります。(一定の非課税枠あり)
ただ、厳密にいうと、死亡退職金は被相続人の死亡時に所有していた相続財産ではありませんが、被相続人の死亡に起因して支払われるため、相続したものと同じとみなされます。(これを『みなし相続財産』といいます。)
(2)特殊事例(退職→死亡)
本来、退職金課税の一連の流れは
① 生前に現役を退き、退職金の支払いを受ける→退職所得課税(所得税課税)
② ①後に死亡し、所得税差引後の現金が相続人に渡る→相続税課税
となるはずです。
この取扱いを踏まえると、生前退職したが、相続時に支給が確定していないものは、そもそも被相続人の相続財産ではなく、いわば財産が宙に浮いた状態となります。
つまり、相続税課税でなく、相続人達が臨時的に取得した一時所得として、所得税課税されるのが妥当なのではないかという見解があります。
ただ、みなし相続財産の取扱いは、本来は相続財産ではありませんが、財産を相続したこととなんら変わりがないということで、相続で取得したものとみなしましょうという取扱いになっています。
以上のことから、生前退職の場合も、死亡退職した場合となんら状況は変わりませんので、死亡退職金の範囲を『死亡退職』に限らず、『生前退職』も含むという取扱いになっているのです。
【参考】そもそもなぜ、死亡後3年以内の支給に限定されているのか
趣旨は大きく2つあります。
・相続開始時に支給額がたとえ未確定であったとしても、相続したものとみなす以上、支給されること自体が当然に予定されていなければならないため
・所得税でなく、相続税で課税する以上、相続税として課税可能な期間内に支給額が確定するものでなくてはならないため
つまり、死亡退職金の支給確定が相続開始時より先過ぎると、その取得要因として、相続と結びつけるのは少々無理があるということになります。
【2】弔慰金の名目で払えば全額非課税にできるのか!?
弔慰金が遺族に支払われた場合の原則的な取扱いは、故人を弔い、遺された家族を慰める性質をもつ金銭であるため全額非課税となります。
ただ、その性質を利用し、名目は弔慰金であるものの、実態は死亡退職金の支払いというケースがあり、その判定を巡り争われることも少なくありません。
そこで、弔慰金として支給されるものについては、下記の算式により、(B)及び(D)を死亡退職金として課税し、(C)を弔慰金として非課税とする取扱いになっています。
(A)-(B)-(C)= (D)
(A)支給を受けた弔慰金額
(B)相続税法基本通達3-18、3-19により、実質的に死亡退職金と認められる金額
(C)業務上の死亡:普通給与※の3年分 業務外の死亡:普通給与※の6月分
(D)死亡退職金として、みなし相続財産になる部分
※普通給与とは、賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、各種手当の合計)を言います。
中でも(C)において、業務上の死亡と一言で言っても、何が業務上の死亡に当たるのでしょうか。
相続税法基本通達3-22では、業務上の死亡の意義を以下のように示しています。

つまり、簡単にいうと、死亡原因が業務と深い関係性にある場合を業務上の死亡と判断することになります。
例えば、業務上の死亡について、次の5つの例示が示されています。
①自己の業務遂行中に発生した事故により死亡した場合
②自己の担当外の業務であっても、雇用主の業務を遂行中に発生した事故により死亡した場合
③出張中や赴任途上に発生した事故により死亡した場合
④自己の従事していた業務により、職業病を誘発して死亡した場合
⑤作業の中断中であっても、業務行為に不随する行為中の事故によって死亡した場合
なお、昭和48年9月以降、通勤災害についても、業務上の災害に準じて、保険が給付されるため、相続税の課税上も、通勤途上の死亡も業務上と同様の取扱いになります。
【弔慰金】裁決事例の紹介
ただ、業務中に死亡したとしても、業務と死亡との間に因果関係がないとして、『業務上の死亡』に該当しないという裁決事例を3つご紹介します。
【第1例】
乳業会社の専務取締役であった被相続人が、会議に出席中、突然死亡しました。
これに対し、遺族は会議に参加したことによる強度の精神的緊張、興奮が死亡の要因となったので、業務上の死亡であると訴えました。
しかし、被相続人の死亡が会議参加による強度の精神的緊張や興奮であるということが推測できないとして、業務上の死亡には該当しないとして課税処分が言い渡されました。
(国税不服審判所 昭和57年8月13日裁決 裁決事例集 No.24 – 127頁)
【第2例】
会社社長が自社の工場視察の際、階段から滑り落ち、全身打撲(第一事故)をしたのち、休日に散歩中転倒し、顔面等を強く打ち入院することになりました。(第二事故)
そのまま入院先の病院で亡くなるという結果になり、会社は業務上の死亡(第一事故が原因)として、弔慰金を遺族に支給しました。
しかし、被相続人の死亡が業務上の死亡であるとする医学的な根拠がない、客観的に見ても死因は散歩中の転倒によることが明らか等の理由から、業務上の死亡には該当しないとして課税処分が言い渡されました。
(国税不服審判所 昭和62年12月1日裁決 東審事例集 V-93頁)
【第3例】
倒産寸前の会社代表者が、会社再建のため、自身にかけた生命保険目的の自殺を行いました。
債権者や従業員の立場を考え、自らを犠牲にし、経営責任を全うしようとした自殺であるため、納税者側から業務上の死亡に該当するとの主張がされました。
しかし、その自殺が社会通念上、何らかの必然性があったとは認められず、業務上の死亡には該当しないとして課税処分が言い渡されました。
(国税不服審判所 昭和56年6月24日裁決 東審事例集 V-55頁)
以上、3事例はいずれも業務上の死亡とは認められなかった事例ですが、審判所の判断をよく検討すれば、業務上の死亡と認められるためのポイントがよく分かる内容でした。
いずれにも共通して言えることは、『死亡の要因が業務にあるとする医学的な根拠が必要』ということになります。
いかがでしたでしょうか。
死亡退職金・弔慰金の税務上の取扱いは、非常にグレーな部分が多く、専門家によっても結論が分かれます。
いずれも非課税になる要素があり、納税者にとっては大変ありがたい制度ですが、適用に当たっては専門家監修のもと、しっかりとした理論武装をし、有無を言わせない対応をしていくことが重要になります。
【死亡退職金 根拠条文】
・相続税法第3条第1項第2号 (相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 退職手当金・功労金等)
・相続税法基本通達3-30 法第3条第1項第2号に規定する「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」とは、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいい、実際に支給される時期が被相続人の死亡後3年以内であるかどうかを問わないものとする。この場合において、支給されることは確定していてもその額が確定しないものについては、同号の支給が確定したものには該当しないものとする。
・相続税法基本通達3-31 被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、その支給されるべき額が、被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するのであるから留意する。
【弔慰金 根拠条文】
・相続税法基本通達3-18
・相続税法基本通達3-19
・相続税法基本通達3-20
・相続税法基本通達3-21
・相続税法基本通達3-22
▼国税庁HPを参照▼
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/03.htm