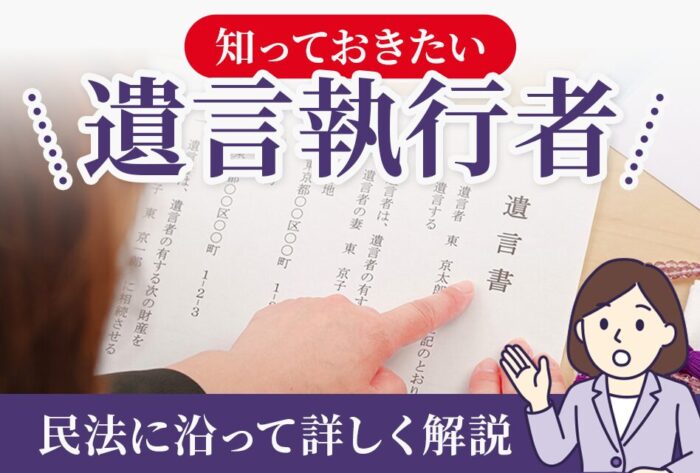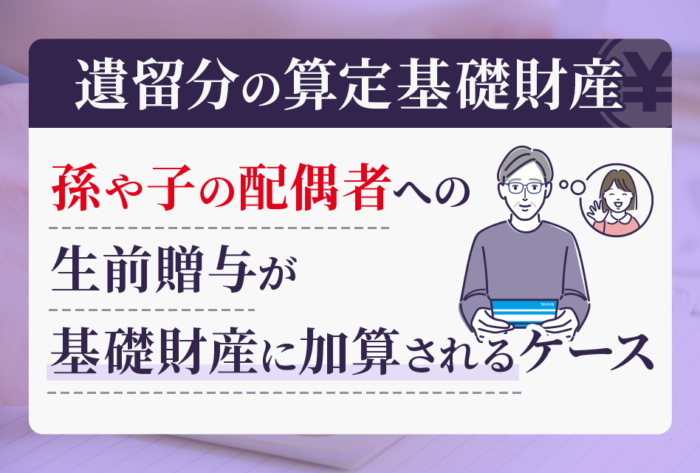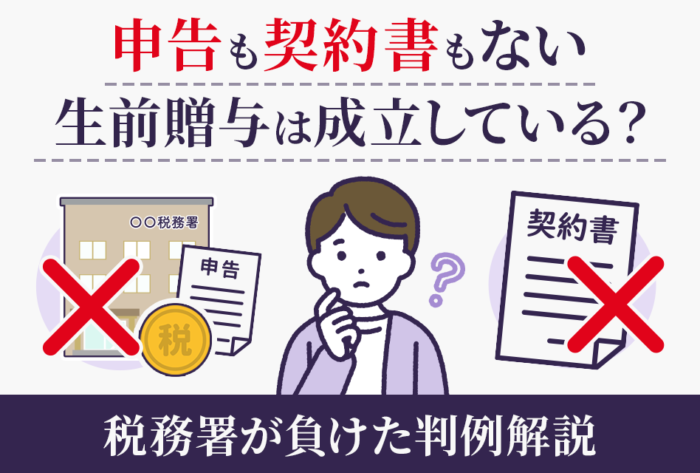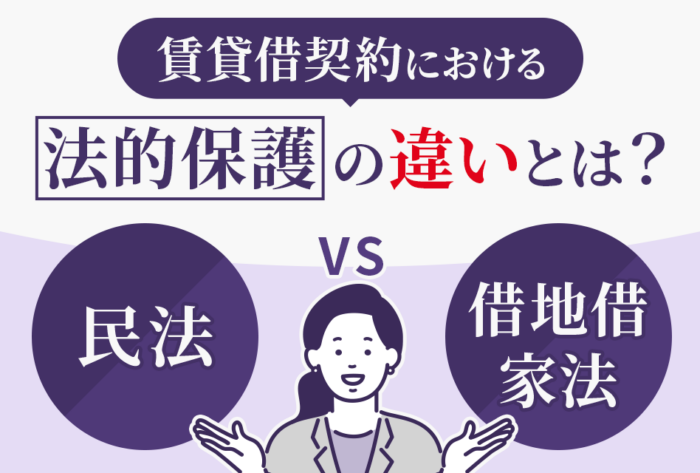未成年者に対する贈与は可能ですが、贈与契約や贈与税の申告・納付方法には注意すべきポイントが多数存在します。
本記事では、税務実務上の観点から、未成年者への贈与の具体的な手続き、契約書の作成方法、贈与税の取扱いについて、事例を交えて詳しく解説します。

大手監査法人にて会計監査業務に従事した後、 円満相続税理士法人に入社。 円満な相続の実現をサポートするため、 金融機関等でセミナー講師も担当している。 詳しいプロフィールはこちら
未成年者に対する贈与の流れと実務上のポイント
贈与契約は民法上の契約行為(法律行為)であるため、財産を渡す人と受け取る人双方の合意が必要です。ただし、未成年者は原則として単独で法律行為を行えないため、通常、親権者が未成年者の代理人として贈与契約を締結します。
未成年者に対する贈与の流れについて、あるご家族を例に解説します。
■ 事例:祖母から3歳の孫への現金贈与
贈与者:祖母、円満 花子(甲)
受贈者:孫、円満 次郎(乙・3歳)
(単独)親権者:乙の母、円満 すみれ(丙)
贈与財産:銀行預金500万円
【Step1】贈与契約書の作成(親権者が代理契約)
一般的には、下記内容を記載します。
・贈与者と受贈者
・贈与財産
・贈与日
・贈与者と受贈者の住所・氏名
※未成年者に対する贈与の場合、親権者(丙)が代理人として贈与契約を締結していることがわかるように、親権者(丙)の住所・氏名も記載します。

なお、未成年者、特に乳幼児など意思表示が困難な年齢の場合、受贈者の署名欄も親権者が代筆して構いません。その際は、親権者が署名した名前の下に、「親権者〇〇が代筆」と明記しておくことで、第三者(税務署等)から見ても形式的な瑕疵がないことを明示できます。
※弊社の公式LINEにご登録いただくと、登録特典として贈与契約書の雛形を無料でプレゼントしていますので、是非この機会にご登録ください♪
民法第549条(贈与)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
【Step2】実際の送金(名義預金に注意)
契約書の作成後、祖母(甲)の名義口座から、孫(乙)の名義口座へ500万円を振り込みます。
⚠ 未成年者である受贈者の親権者がお金を管理する場合、「名義預金」と判断される可能性があります。「名義預金」として認定されてしまうと、多額の相続税とペナルティを追加で支払うことになってしまうので、未成年者である受贈者名義の預金口座で、お金を管理してください。
【Step3】贈与税申告(親権者が代理)
贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の間に、親権者が代理で贈与税申告を行います。
例:2025年7月1日に贈与→2026年2月1日〜3月15日の間に申告が必要です。
【Step4】贈与税の納付(親権者が代理)
贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の間に、親権者が代理で贈与を納付します。
例:2025年7月1日に贈与→2026年2月1日〜3月15日の間に納税が必要です。
申告と納税は、期限内であれば、どちらが先でも問題ありません。
500万円の贈与を受けた場合、53万円の贈与税を支払う必要があります。
(500万円 - 110万円)× 20% - 25万円 = 53万円
⚠ 未成年者への贈与は「特例税率」の対象外です。必ず「一般税率」を適用してください。詳しい解説は、後述のQ&Aをご参照ください。
未成年者に対する贈与に関するQ&A
Q. 贈与契約書は作成する必要がありますか?
A.贈与契約は口頭でも成立しますが、未成年者に対する贈与は特に贈与契約書を作成しましょう。
契約書を作成し保管しておけば、税務調査の際も贈与の事実を客観的に示すことができます。
Q. 生まれてから18歳で成人するまで100万円を毎年贈与しようと考えているのですが
毎年100万円贈与する旨の契約書を1枚作成すればいいですか?
A.贈与契約書は贈与の都度作成してください。
毎年100万円贈与する旨の契約書1枚を作成してしまうと、定期贈与に該当し、1,800万円(18年間×100万円)を100万円に分けて18年で贈与するという契約をしたと見なされ、高額な贈与税を支払うことになります。
Q. 贈与契約書作成時の留意点を教えてください。
A.受贈者および受贈者の親権者欄にて、それぞれが署名捺印してください。
受贈者が幼い子どもの場合は、親権者が代筆して問題ありません。
親権者が書いた名前の下に「親権者〇〇が代筆」と記載してください。
弊社の公式LINEにご登録いただくと、登録特典として贈与契約書の雛形を無料でプレゼントしていますので、是非この機会にご登録ください♪
Q. 贈与税(暦年課税)の申告は、どうすればいいですか?
A.基礎控除(110万円)を超える財産を受け取る場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出しなければなりません。
未成年者に対して贈与している場合は、原則、親権者が代理で申告を行います。
Q. 贈与税には、一般税率と特例税率の2つの税率があるようなのですが、どちらを使うのが正しいのでしょうか?
A.特例税率の対象者に該当しない場合、一般税率を適用してください。
特例税率は、贈与により財産を取得した人(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者に限る。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した場合に適用できます。そのため、未成年者に贈与をした場合は、一般税率を適用することになります。
また、18歳かどうかは贈与年の1月1日時点で判定するため、年の中途で18歳になる場合は、一般税率を適用することになります。
Q. シンプルな贈与であっても税理士さんに申告をお願いしたほうがいいですか?
A.税理士に申告をお願いしたほうが良いかと思います。
相続税対策・生前対策は様々な選択肢・リスクなどが存在します。例えば、生前贈与加算という制度を知らずに贈与を続けて、相続が発生した時に期待通りの効果が発揮しなかった失敗事例を多く見てきました。相続・贈与は多角的な視点からの検討が必要となるため、相続に強い税理士さんにご相談することをお勧めいたします。
未成年者に対する贈与に関するQ&A(実務家向け)
Q. 親権者の代理なく、未成年者が受贈者として贈与契約を締結することはできますか?
A.一定の年齢以上であれば可能です。
未成年者は、原則法律行為ができません。
携帯の契約を親の同意なく、子ども自身が締結するといったことはできない訳です。
ただし、民法第5条の但書き「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」を根拠に、未成年者は一部の法律行為が可能であると解釈されています。
民法第5条(未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」とは、どのような行為なのでしょうか?そもそも、未成年者が原則法律行為をできないのは、悪い大人から未成年者を保護することが背景にあります。
それでは、親が子どもに現金500万円を贈与する行為に、危険性は考えらえるでしょうか?子どもは現金500万円を手に入れるだけであり、何かの連帯保証等を負うわけではありません。これが、「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」の一例になります。
つまり、親が子どもに現金を贈与するような未成年者に対する贈与は、「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」に該当するため、法律上可能と解釈されています。
※ただし、負担付贈与のように、贈与をする代わりに一定の負担を受贈者に負わせる贈与は、私見ですが難しいと考えます。
一般的には小学生低学年から意思能力が備わりだすとされており、シンプルな贈与であれば、1つの目安となると考えます。なお、非常に古い判例ですが、土地の売買契約にて、7歳3カ月の未成年者が売主に対して行った、土地の所有権を取得する旨の意思表示が有効であるとされたものがあります。
私見ですが、少なくとも中学生になるまでは、親権者が代理したほうが無難であると考えます。
Q.(単独)親権者甲は、自身の子ども乙(未成年者)に対して、現金300万円を贈与する予定です。(単独)親権者甲が子乙を代理して、自らと贈与契約を締結することは可能なのでしょうか?
自己契約の禁止や親権者の利益相反行為の禁止などにより契約が無効になることはありますか?
A.自己契約の禁止や利益相反行為の禁止に抵触せず、贈与契約が無効になることないと考えます。自己契約の禁止の趣旨は、同一人物が契約を締結すると未成年者よりも、親権者の利益を優先する懸念があるためです。単純贈与であれば未成年者は単に利益を得る法律行為であるため、自己契約の禁止に該当しないと考えます。
また、利益相反も、子どもが受贈者になる単純贈与であれば、客観的に子どもの利益になるため、利益相反行為に該当しないと考えます。
おわりに
今回は、未成年者に対する贈与について解説しました。
未成年者に対して贈与は問題なく実施することができます。しかし、贈与契約書の作成や贈与の実行方法に注意しないと、将来税務調査で問題となり、追加で税金を払うことになる可能性があります。是非、上記記載の手順に従って、贈与を実行してみてください。
もし、この記事を最後まで読んでいただいて、少しでも相続税(贈与税)対策に不安を感じましたら、是非、円満相続税理士法人にご相談ください!
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
※最終更新日:2025年7月15日