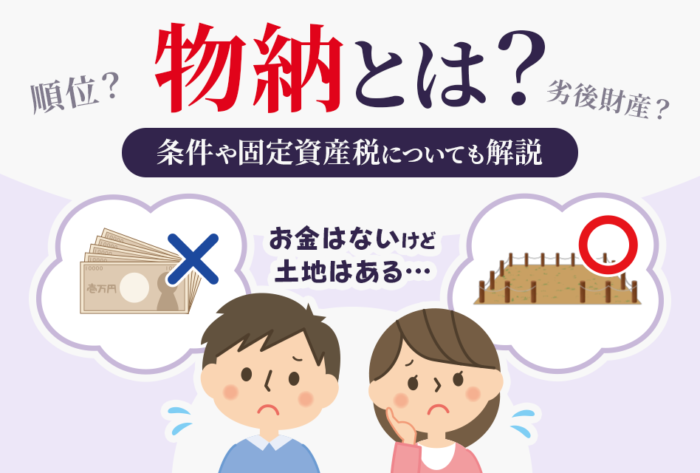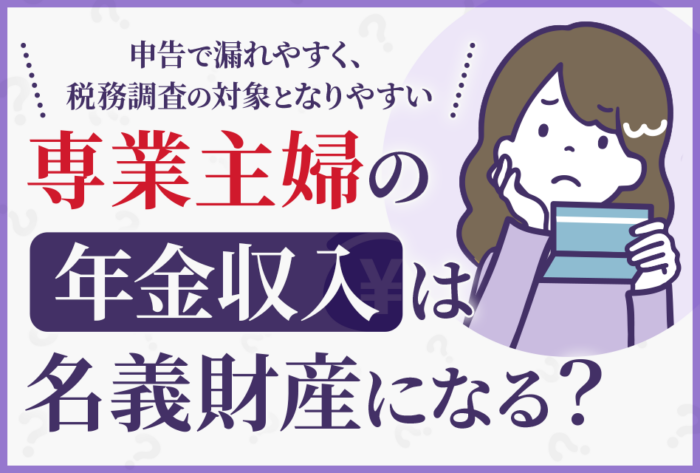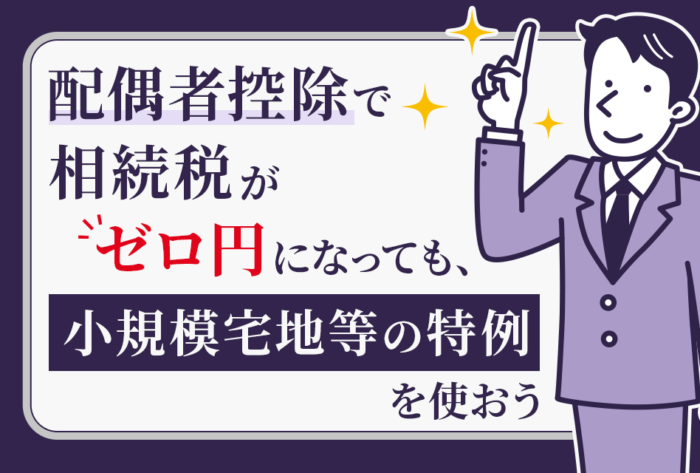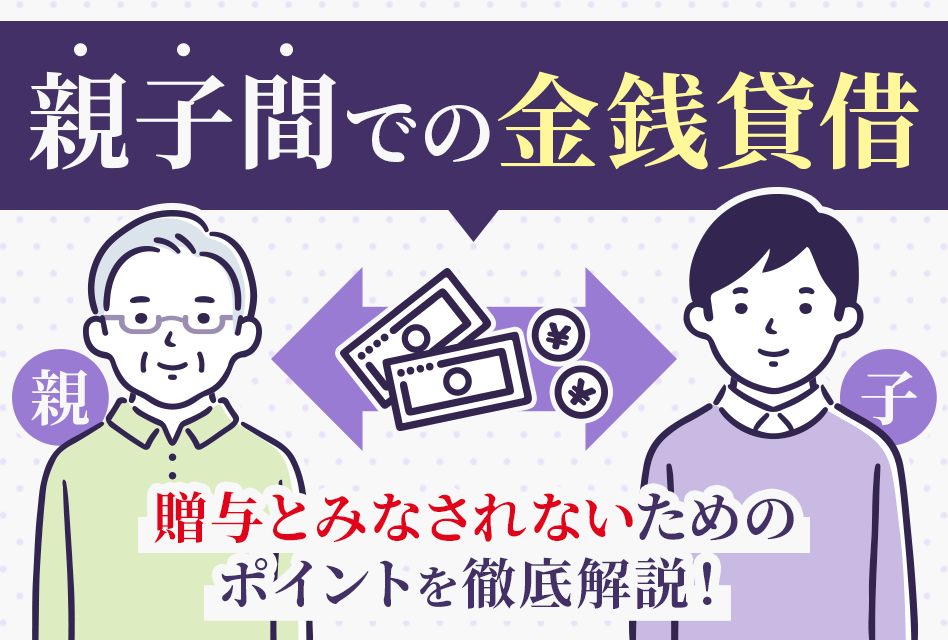
こんにちは、税理士の枡塚です!

円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
親子間、親族間でお金の貸し借りをすることはよくあることです。特に、事業を始める、マイホームを購入する等、多額に資金が必要になった場合に、資金を調達する手段として、『親から借りる』という選択をする方は多いのではないでしょうか。
しかし、馴れ合いの関係から返済をきちんとしない場合など、贈与と取り扱われ、贈与税が課税される可能性があります。
親子間の金銭の貸借は、贈与税が課税されますか?
実態として、金銭の貸借である場合には、贈与税が課税されることはありません。
ただし、その関係性から『ある時払いの催促なし』や『出世払い』のような第三者間ではありえない取引をしている場合には、贈与として取り扱われます。
贈与と取り扱われないように、以下のような書類や条件を整え、実態として金銭の貸借であることを立証できるように準備しておくことが重要です。
金銭消費貸借契約書を作成すること
貸す側と借りる側の間で交わされる契約書のことです。貸し借りする金額、返済期限、返済方法、利率など金銭貸借の条件を記載し、双方が署名捺印します。
親族間のため、借用書を作成される方も多いです。借用書と金銭消費貸借契約書は似ているものですが、異なる点があります。
それは、借用書は主に借りた側が作成し、返済の約束を記したものということです。
そのため、法的に有効な証拠として効力が強いのは、双方が署名捺印をしている金銭消費貸借契約書であると考えられていますので、金銭消費貸借契約書の作成をお勧めしています。
また、金額によっては、収入印紙の貼付が必要になりますが、親子間だからといって省略せず、貼付しましょう。印紙税は、特定の取引や契約を証明する文書に対して課される税金です。もちろん、金銭消費貸借契約書も対象に含まれており、親子間だからといって免除されるものではありません。
印紙を貼付しない場合であっても契約書自体が無効になるわけではありませんが、過怠税が科される等ペナルティの対象になります。
返済計画が現実的であること
85歳の父から、返済期間を35年として5,000万円を借りようと考えています。この条件で金銭貸借をした場合、返済完了を迎える頃、父は120歳になっています。
また、収入や貯蓄のない方が多額の金銭を借り入れ無謀な返済計画を立てていた場合、どのように返済をするつもりだったのかが問題になります。
初めから返済する気がなかったのでは?とみられ贈与と取り扱われる可能性がありますので、実現可能な常識的な範囲で返済計画を立てましょう。
契約書通りに返済がされていること
『ある時払い催促なし』『出世払い』は贈与と取り扱われてしまいます。可能な限り、契約書通りに返済をしましょう。また、返済は現金手渡しではなく、銀行振込とし、返済の事実が記録として残るようにしておくのが良いでしょう。
利息の支払いがされていること
家族間で貸し借りをしている場合には、『まぁ利息までは…』と利息を取らないケースが多いかと思います。
しかし、利息を取らない場合には、利息相当額が貸した人から借りた人への贈与とみなされてしまいます。
ただ、贈与税には110万円の基礎控除枠があることから、少額の利息であれば、この枠内でおさまるため、実質贈与税は課税されないと考えられます。
ただし、他にも生前贈与を検討している場合には、利息についてもきちんと支払いをしましょう。
まとめ
当人同士は、『貸したよね?』『うん、借りた』と認識していても、その実態が『あげた』『もらった』となっている場合には、容赦なく贈与と取り扱われてしまいます。
口約束での貸し借りや、ある時に返してくれたらいいよといった内容では、親子間は良好であるものの、思わぬ無駄な税金の支払いをする羽目になるかもしれません。
また、教育資金贈与や住宅資金贈与、相続時精算課税制度等を利用して、貸し借りではなく、はじめから贈与してしまう方が良い場合もあります。多額の資金を子や孫に…とお考えの場合は、是非一度円満相続税理士法人にご相談ください。