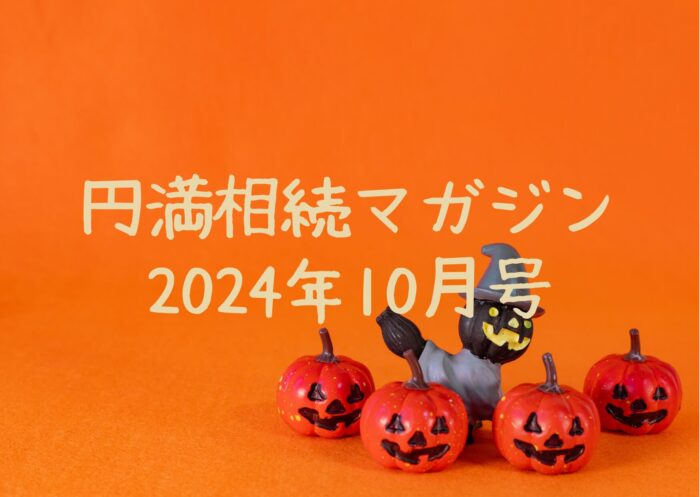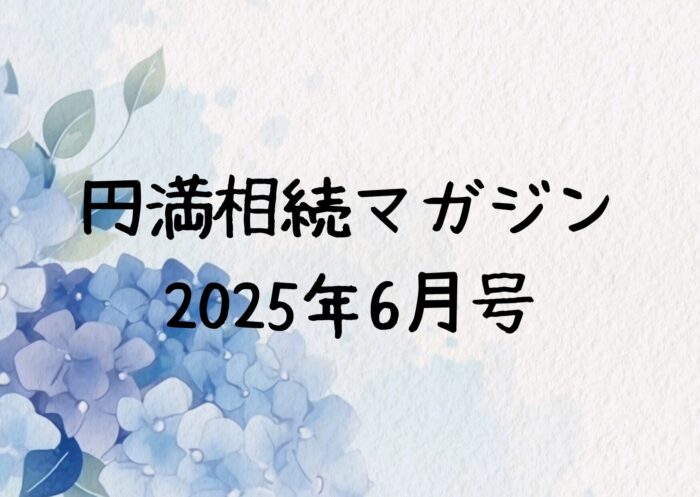今月のニュース
2026年1月12日(月・祝)セミナー開催!
①13:00~14:00 節税になる不動産の「売却ベストタイミング」マニュアル! 講師:円満相続税理士法人 桑田税理士
②15:00~16:00 相続登記義務化と相続手続き完全解説! 講師:行政書士法人オーシャン 岡田行政書士
どちらかだけでも、両方でもご参加いただけます。 参加費は無料です。
開催場所:円満相続税理士法人 青山支店(人数によっては、近隣の会議室を借りる可能性がございます。最終的な開催場所は、開催1週間前にご連絡いたします)
不動産は、売るタイミングで使える税金の特例が大きく変わります。 前半では、税理士桑田が、税金で得する不動産を売るタイミングを例を交えて解説します。
相続登記をまだしていない不動産をお持ちではありませんか? 後半では、相続登記の義務化と、最新の相続手続きについて、徹底解説します。 皆さまのご参加を、お待ちしております♪
2025年 年末年始休業のお知らせ
2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)
2026年1月5日(月)9時から通常営業とさせて頂きます。
年末年始休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、2026年1月5日(月)午前9時以降より順次ご連絡させていただきます。
円満相続塾2025年が終了しました!
先日、弊社が提供している円満相続塾のカリキュラム全12講が無事に終了しました!
東京事務所の野本です。
相続のプロフェッショナルを目指す人向けのオンラインセミナー「円満相続塾」を2025年8月より開講しておりましたが、先日無事にカリキュラム全12講が終了しました!
また、オフラインにて受講生の皆さんとお疲れ様会の開催をいたしました!
普段はオンラインでの講義でしたので、受講生の皆さんと交流をする機会がほとんどなかったのですが、東京・大阪にてイベントスペースで開催し、両日ともに受講生の皆さんとたくさん交流することができました。
2025年度の円満相続塾はありがたいことに大盛況で締めくくることができ、代表の橘をはじめ弊社一同、改めて感謝申し上げます。
録画講義の販売もしていますので、ご興味のある方はぜひご検討いただけますと幸いです。
早いもので今年も1年が終わろうとしていますね…インフルエンザも流行っておりますので、皆さま健康には気を付けて仕事納めしてくださいね!では、よいお年を!


冬の出張相談会 12月開催のお知らせ(関西地域)
大阪事務所の北尾です。
円満相続税理士法人では、下記の通り「冬の出張相談会」を開催いたします。
相続が発生しており、かつ申告のご依頼を検討している方を対象に、税理士による個別相談を無料で承ります。
◆開催エリア
京都/神戸/姫路/奈良/和歌山/高松
◆ 日程
京都:12/19(金)
神戸:12/2(火)
姫路:12/12(金)
奈良:12/1(月)
和歌山:12/8(月)
高松:12/5(金)
◆面談時間
9:00〜18:00(1時間30分程度・事前予約制)
定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。
お早めのご予約をお願いいたします!
【2025年10月スタート】公正証書遺言がオンラインで作成可能に!デジタル公正証書遺言とは?【税のトピック1】
東京事務所の久保です。
遺言書がオンラインで作れるようになったと聞きましたが、詳しく教えてください!
2025年10月から、公正証書遺言の作成手続きがオンラインで対応可能になります。終活・相続をご検討の方には大きな変化ですので、ぜひご一読ください!
従来の公正証書遺言と、これからの「デジタル公正証書遺言」
これまで、公正証書遺言を作成するには公証役場に出向き、対面で手続きを行う必要がありました。
・公証人との対面による面談
・証人2名の立会い
・平日日中に公証役場へ行く時間を確保
といった手間がかかっていました。
しかし、2025年10月からは手続きがオンライン化され、自宅や施設からの作成が可能になります!
デジタル公正証書遺言でできること【3つのポイント】
・自宅・病院・介護施設などから遺言書が作成可能に
・証人2名も、別々の場所からオンライン参加が可能
・署名・交付もデジタルで完結(希望により紙での交付も可)
法改正の背景と概要
この制度は、2023年6月に成立した「デジタル社会の実現に向けた関係法律の整備法」に基づき導入されます。
信頼性の高い「公正証書遺言」の仕組みはそのままに、利便性を高めることが目的です。
デジタル公正証書遺言を作成する手順【ステップ別】
公証役場への事前相談(オンライン対応可能か確認)
オンラインでの申請・資料の電子提出(電子署名が必要)
遺言書案の確認(メール等でやり取り)
ウェブ会議による本人確認と「口授」(内容の口頭説明)
電子公正証書の作成と交付(交付は従来通り紙でも可能)
注意点・確認しておきたい5つのこと
1. ウェブ会議は「必須」ではない
オンラインでの公正証書遺言作成は非常に便利な制度ですが、ウェブ会議による手続きは必ずしも実施されるとは限りません。
ウェブ会議を利用できるのは、
・遺言者が希望した場合
・かつ、公証人がその方法で適切に手続きを行えると判断した場合
に限られます。
特に、以下のような事情がある場合は、対面による手続きが求められる可能性があります。
・本人確認に不安がある(成りすましの懸念など)
・遺言者の意思能力を慎重に確認する必要があると判断される など
そのため、オンラインだからこそ、本人確認は一層慎重に行われることが予想されます。
実際には、マイナンバーカードや運転免許証を用いた顔認証、ウェブ会議での面談などにより、不正作成のリスクを低減するための複数の対策が講じられています。
今後の運用状況に応じて、さらなる安全対策が導入されることも想定されます。
2. すべての公証役場で一斉開始とは限らない
制度は2025年10月から開始されますが、システム対応の関係で一部の公証役場のみが当初対応可能なケースがあります。
公証役場へ事前確認しておくのがおすすめです。
3. 「口授」は従来通り必要
遺言内容は、遺言者自身が自分の言葉で説明(口授)しなければなりません。
ただ「はい」と答えるだけでは無効になるおそれがあります。
4. 証人2名の立会いも必須(オンラインでも)
推定相続人や遺言によって遺産を引き継ぐ人、その配偶者・直系血族は証人にはなれません。
5. 電子署名の準備が必要
オンライン申請には電子署名(マイナンバーカード等)が必要です。
また、以下の機材の事前準備も必要です。
ウェブ会議に参加可能なパソコン(スマートフォン・タブレットは使用できません)
電子サイン用のタッチ入力可能なディスプレイ又はペンタブレット+電子ペン
③①のパソコンで利用可能なメールアドレス
まとめ
2025年10月から始まる「デジタル公正証書遺言」は、手続きのハードルを下げる後押しとなる制度です。とはいえ、利点がある一方で、制度としての信頼性や安全性が十分に確立されるまでには、一定の時間が必要と考えられます。
特に、公正証書遺言は重要な法的効力を持つ書類です。
「形式的には整っているが、実は本人の意思に基づいていなかった」といったことが起こらないよう、今後の制度運用や技術的な改善も注目されるところです。
不動産の共有を避けるべき理由3選【税のトピック2】
名古屋事務所の土屋です。今回は共有不動産についてのお話です。
遺産分割協議を成立させるため、土地や建物を共有名義としてしまう方がいらっしゃいますが、不動産の共有はメリットよりデメリットの方がはるかに大きいです。
相続の際には可能な限り不動産の共有は避けたいところです。このコラムでは、共有の何がいけないのか解説していきたいと思います。
不動産の共有とは
不動産の所有権を複数の人が保有している状態を言います。具体的には、所有権がAさん1/2、Bさん1/2のように複数で保有することです。
ウチの土地は長男と二男で1/2ずつだから、東半分を長男が所有していて、西半分を二男が所有していると考えていますが…
それは正しい認識ではありませんね。その前にまずは「共有」の概念を理解しましょう!
1/2ずつで共有している状態というのは、その土地のどの部分についても1/2の所有権があるということです。
私は「共有」の概念を説明する時、いつも次のようにコーヒーとミルクで例えて説明しています。
空のコップがあり、このコップにコーヒーとミルクをコップいっぱいになるまで同量を注いで混ぜます。
そうするとミルクとコーヒーの割合が1/2ずつのミルクコーヒーができあがります。
このミルクコーヒーは、コップの中のどの部分を取り出してもミルクとコーヒーが混ざった味がします。コップの上部を取り出せばミルクの味しかしない、下部を取り出せばコーヒーの味しかしない、なんてことにはなりません。ミルクとコーヒーが混ざってしまっているからです。
コップの中のどの部分を取り出してもミルクコーヒーです。これが「共有」の概念です。
土地の話に戻しますが、兄弟で共有ということは、その土地のどの部分を取り出しても長男1/2、二男1/2の所有権が存在します。
東半分は長男の所有権しかない、西半分は二男の所有権しかない、なんてことにはなりません。
「共有」の概念はよく理解できました。では、どんな時に問題が生じるのですか?
問題が生じる場面を3つ紹介します。
1.土地が売れなくなる
共有しているその土地を売却するには、共有者全員の合意が必要です。
長男が売りたがっていても、二男が売りたくなければ、売りに出すことができません。
手続き的には長男の共有持分1/2だけを売りに出すことは可能ではありますが、そんな不動産は誰も買いません。実際に共有持分1/2を売りに出している不動産は今まで見たこともありません。
2.土地の使用にも共有者の同意が必要
長男は共有しているその土地を駐車場にして賃料収入を得たいと計画していても、実行するには二男の同意が必要になります。
一方、二男は駐車場ではなく、アパートを建築して賃料収入を得たいと考えていました。二男のアパートの建築計画も長男の同意が必要になります。
こうなると長男も二男もお互いに同意を得ることができないので、土地活用できないまま固定資産税だけ支払っている状況になってしまいます。
3.相続が起こると更に問題が大きくなる
上記のように長男と二男でお互い同意がないまま時間が過ぎて行くと、そのうち共有者のどちらかの相続が始まります。
例えば長男が死亡し、長男の子供2人がその土地を相続したとします。
そうすると、二男はその土地の売却や土地活用したい場合、同意を得なければいけない共有者は2人に増えることになります。
更に二男も死亡して二男の子供2人がその土地を相続すると共有者は4人。
同意を得るのはお互いに更に困難となってしまいます。
このように共有者に相続が発生して次々と共有者が増えてしまうと、そのうち共有者の中に連絡がつかない者が出てきます。
そうなってしまうと全員の合意が得られないので売ることも貸すこともできずに固定資産税だけ支払い続けることになります。
都市部の一等地に老朽空き家が長年放置されたままの土地を見かけることがありますが、だいたいは上記の事情が当てはまります。
以上、不動産を共有するデメリットでした。
次回のコラムでは不動産共有を解消する方法を解説していきたいと思います。
編集後記(橘の日常)
みなさま、こんにちは!税理士の橘です
皆さんは、スマートフォンのパスワードを、家族で共有していますか?
亡くなった父のスマートフォンのロックが解除できないため、財産調査がスムーズにできません…!
最近、このようなご相談が非常に増えていると感じます。 世の中がどんどん便利になり、スマートフォンだけで銀行も証券会社も、さらには借金も管理できる時代になりました。
しかしその反面、いざ、相続が起きたときには、亡くなった方のスマホロックが解除できないと、家族は思い当たる全ての金融機関などに問合せをしなければならず、非常に苦労します。
ただ、実は、このような時代に困る人がでないよう、国としても、色々と新しい制度を導入してくれています。
例えば、亡くなった人の預金口座が、どこの銀行にあるかを一括で照会できる制度であったり、不動産も同じように照会できる制度が始まります。
ここで、急に告知ですが、今月上旬に、ぶっちゃけ相続手続き大全増補改訂版が全国書店で発売されます! 4年ぶりの改定になりますが、思った以上に、書き直すことが多くて自分でも驚きました。

テクノロジーの進化って凄いですね。 相続手続きの最新情報を知っておけば、いざというときに非常に楽になりますので、一度、手に取っていただければ嬉しいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。