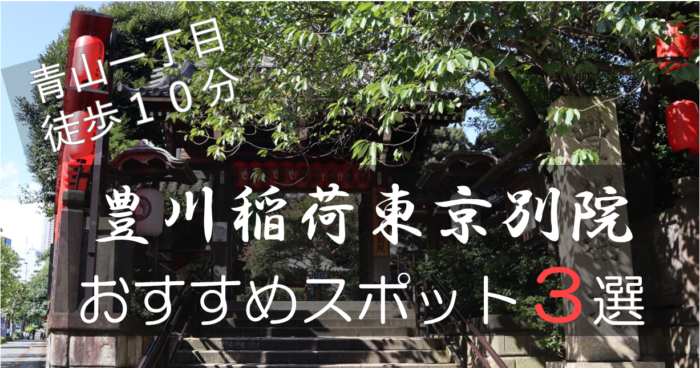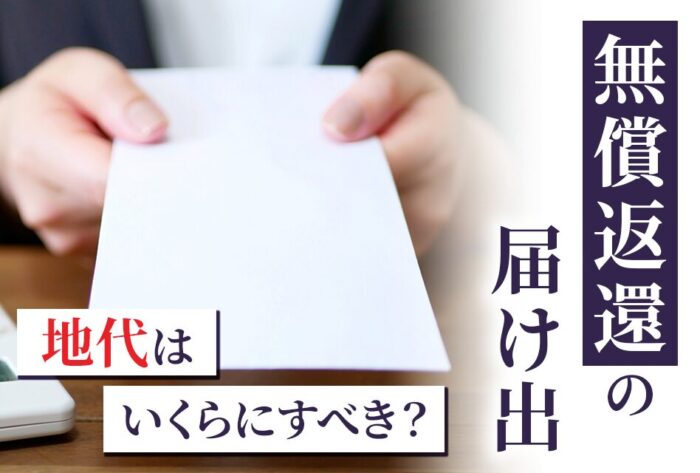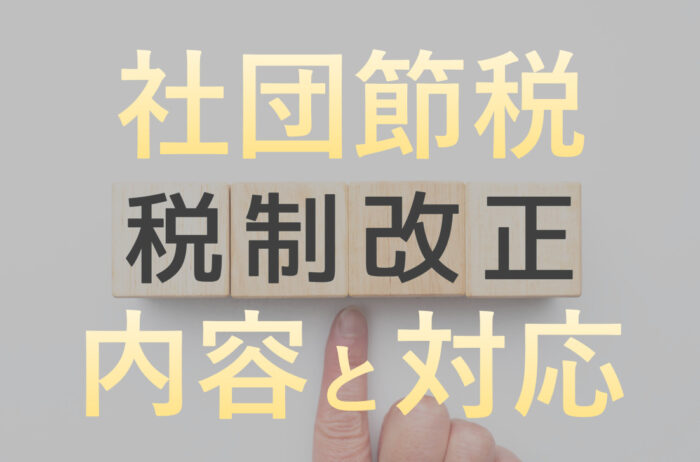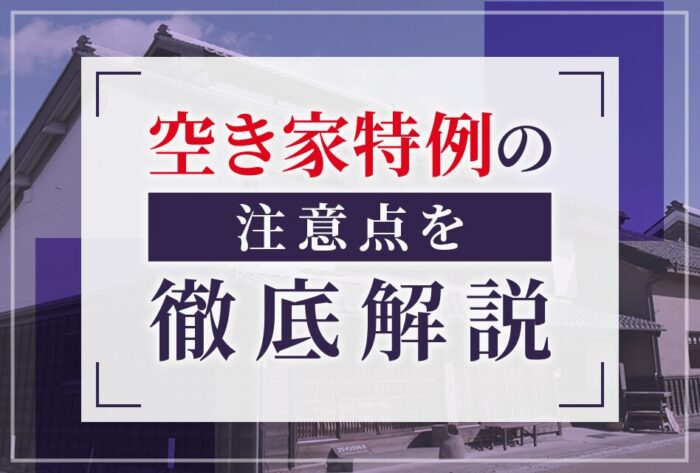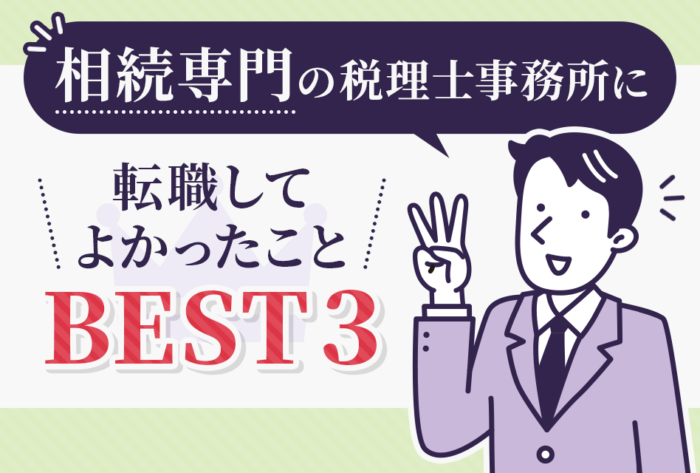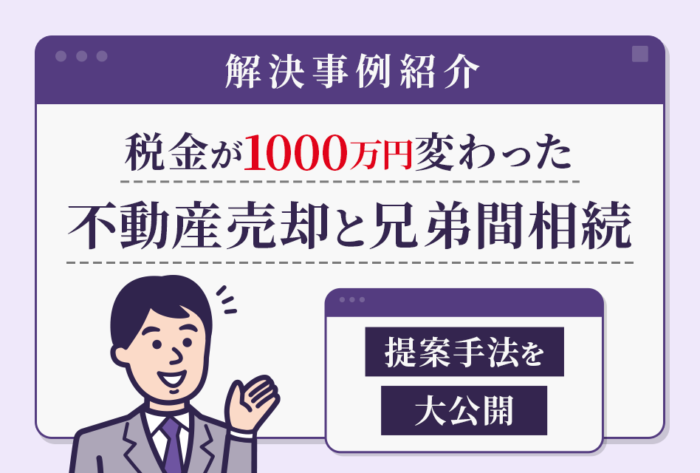円満相続税理士法人 パートナー税理士
相続税申告200件以上、相続不動産の売却でお困りの方を含め3,000人以上のお客様を担当してきた相続専門の税理士。大手税理士事務所で勤めてきた経験と資格の大原にて相続税法の非常勤講師を務めた経験から、金融機関やお客様向けセミナーでは分かりやすさに定評がある。
こんにちは!相続専門税理士の大田です。
2019年7月1日から遺留分が改正されました。
この改正に伴い、所得税の取り扱いが変わり、さらに相続税の取り扱いも大きく変わる可能性が出てきました!
これまで当たり前に使えていた特例が使えなくなったり、税負担が数千万円も変わるなど大きな影響が出てきます。
そこで今回は、改正が相続税に与える影響について解説します!
一般の方はもとより、相続実務に携わる方にとって、必ずためになる話だと思いますので、是非最後までご覧ください♪
遺留分はどう改正されたの?
まず、そもそもの遺留分についておさらいをしたい方は、こちらの記事をご覧ください。
簡単に、今回の遺留分の改正を一言でいうと
『遺留分の清算のやり取りは、全て、お金でやってください。』
という改正です。
これまでは清算のやり取りをする際、不動産などの現物で行うことも可能でしたが、これだと財産が共有になってしまったり、換金できないという問題点がありましたが、改正によってこの部分が払しょくされました。
※原則は、お金での清算となりますが、両者の合意があった場合には、現物で行うこともできます。
もっと詳しく、改正の経緯や所得税などの影響について知りたい方は、こちらの記事で触れていますので、ぜひご覧ください。
相続税への影響とは!?
遺留分の改正が、相続税に与える影響とは、 ずばり「小規模宅地の特例の選択替えができなくなる」という点です。
これだけを聞いても、何のことかさっぱりわからない人が、ほとんどだと思いますので、順番に解説していきます♪
小規模宅地の特例のおさらい
まず、「小規模宅地の特例」ってなんだったっけ、という方に向けて、ご説明しますと、「亡くなった人が自宅として使用していた土地については、配偶者か同居親族であれば、8割引きの金額で相続していいですよ」という特例です!
このほかに、亡くなった方の自宅に限らず、賃貸用不動産や事業用不動産についても適用があります。
内容をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
小規模宅地の特例の選択替えとは
前提として、小規模宅地の特例の選択替えは認められていません。
これはどういうことかというと、例えば、長男が、亡くなった母から自宅とアパートを相続したケースを考えてみましょう。
この長男は、アパートに小規模宅地の特例を適用することを選択して、申告書を税務署に提出しました。

ところが申告期限後に、実はアパートではなく、自宅に特例を適用した方が有利なことに気が付きました。
この時に、「アパートから自宅へ」小規模宅地の特例の選択替えができるのでしょうか。
答えは、NOです。

このように、あとで税額が有利になることが分かって、選択替えをしたかったとしても、修正することは認められないのです。
選択替えが認められるケース
ただし、次のようなケースの場合には、選択替えが認められます。
そもそも選択した土地について特例が適用できなかった場合
これは先程のケースで考えると、アパートが小規模宅地の特例の要件にあてはまらず、そもそも適用できなかった場合です。
この場合には、そもそもアパートから特例を適用できず、正しい申告が出来ていませんでしたので、自宅に特例を使った形に修正してもOKということになります。

遺留分減殺請求があった場合
こちらでは、遺留分減殺請求があった場合に、どのように選択替えができるのかを解説していきます。
前提として、亡くなった方は母、相続人は長男と長女の2人、母は『自宅とアパートを全て長男へ遺す』という遺言書を作っていた場合を考えていきます。
長男は、引き継いだアパートに小規模宅地の特例を使うことを選択して、期限内に申告しました。

長女は、自分が財産を一切相続できないことを不服に思い、長男に対して遺留分の減殺請求を行い、アパートを取得したとします。

この時、小規模宅地の特例はどのようになるでしょうか。
長男はもともと遺留分減殺請求の前は、アパートに小規模宅地の特例を適用していましたが、そのアパートは長女のものになってしまったのです。長男は自宅だけを相続し、長女はアパートを引き継いだことになります。
この場合、長男はアパートから自宅に選択換えが認められるのか?そして新たにアパートを取得した長女は、アパートに特例を使うことが認められるのか?ということが問題になります。
結論、この場合には、両者とも、小規模宅地の特例を適用できます!
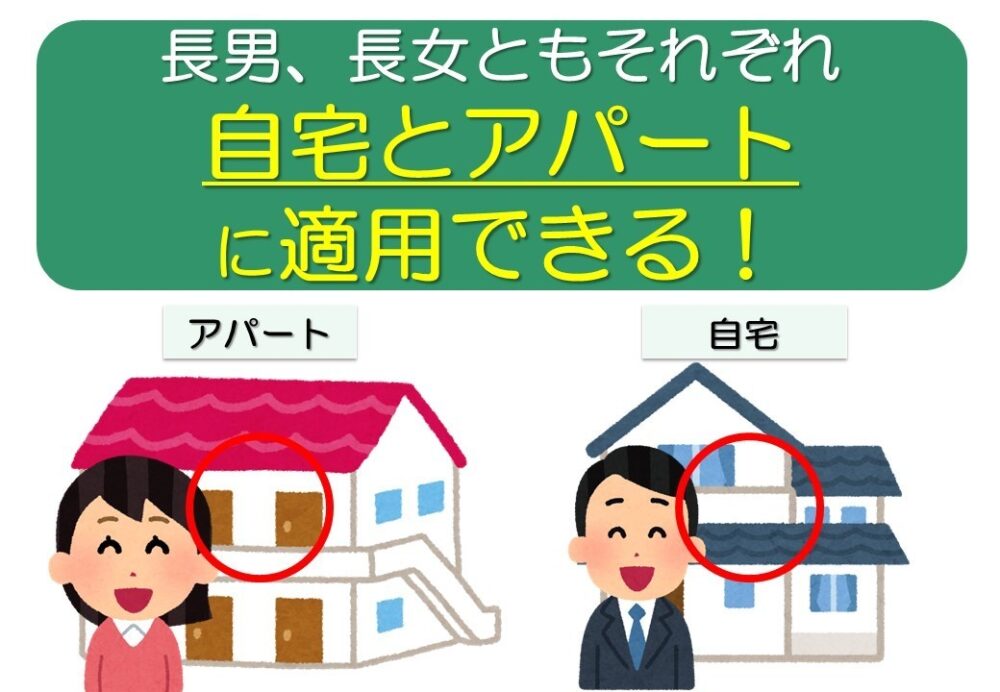
この際、長男は修正申告、長女は遺留分減殺請求が確定してから4カ月以内に更正の請求をする必要があります。
遺留分減殺請求のような後発的な出来事によって、相続の仕方が変わった場合には、選択替えを認めてもらえます。
参考 国税庁質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/04.htm
遺留分侵害額請求(改正後)では選択替えが認められない!
ここまでの前提を抑えていただいたら、いよいよ今回の改正による影響が出る部分について解説していきます。
冒頭でも書きましたが、遺留分の改正が、相続税に与える影響とは、「小規模宅地の特例の選択替えができなくなる」という点です。
これはどういうことかというと、改正前(令和元年6月30日以前に相続発生の場合)は、先ほどのとおり、小規模宅地の特例が使えましたが、改正後(令和元年7月1日以降相続発生の場合)は、長男のアパートから自宅への選択換えは認められず、長女が新たに取得したアパートへの特例適用も認められない形になります。

これは、改正後の遺留分の精算は、金銭で行うことがルール化されたことが背景にあるようです。
これを受けて、遺留分減殺請求という名称が、改正後は遺留分侵害額請求へと変更されました。
これまでは、遺留分として不動産を現物で渡すとしていましたので、選択替えが認められていましたが、改正後は、不動産を渡したとしても、それはあくまで金銭の支払いに代えて引き渡したものであるとして、選択替えを認めないという考え方に変わりました。
要するに、不動産の移転は、「譲渡」であり「相続」で取得したことにならないので、小規模宅地の特例の選択換えも認められないということですね。
ただし、当初申告で長男がアパートで特例の適用を受けていて、その後引き続き、要件を満たしていれば、当初申告の通り、長男がアパートに特例を適用することができます。
※長男が相続税申告期限内に遺留分の精算としてアパートを長女に移転させた場合には、継続所有要件を満たさなくなるため、適用できなくなります。
なので今後、遺留分侵害額請求が起こりそうな案件に当たった場合は、選択替えができないという前提で、コンサルティングを行う必要がありそうですね!
ちなみに、遺言書がある場合に、遺留分侵害額請求ではなくて、話し合いがまとまれば、遺産分割協議で兄弟間の財産を分け合うこともできます。
ただこの際に、上記の例のように、アパートだけを長女が相続するとしてしまう場合は、相続税のほかに、贈与税が課税されてしまう可能性があるので注意してください!
この点についてまとめた記事がありますので、興味がある方はこちらの記事もご確認ください!
終わりに・・・
ということでいかがでしたでしょうか。
円満相続税理士法人では、このような係争案件を年間数十件取り扱っています。
この記事のほかにも法律家や実務家が知っておかなければならない税金の話をお伝えしていますので、よろしければ一度定期勉強会にご参加いただければ嬉しいです♪