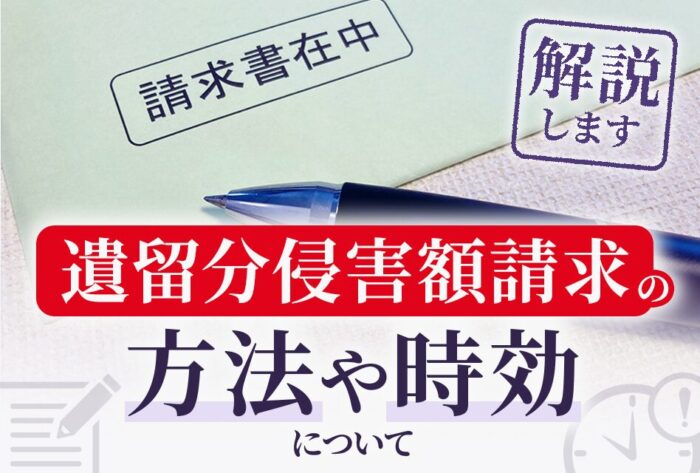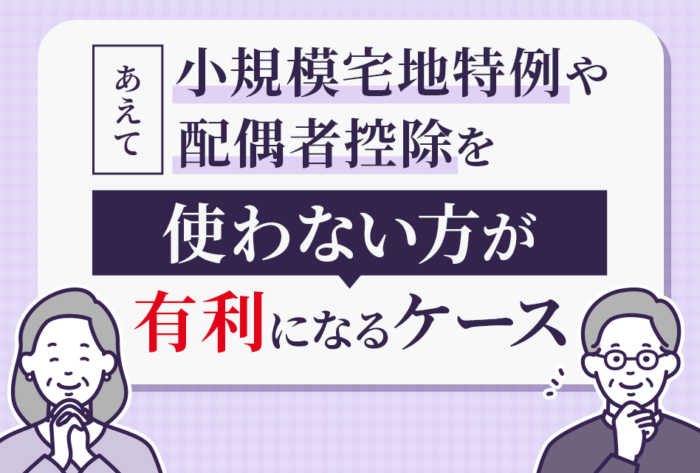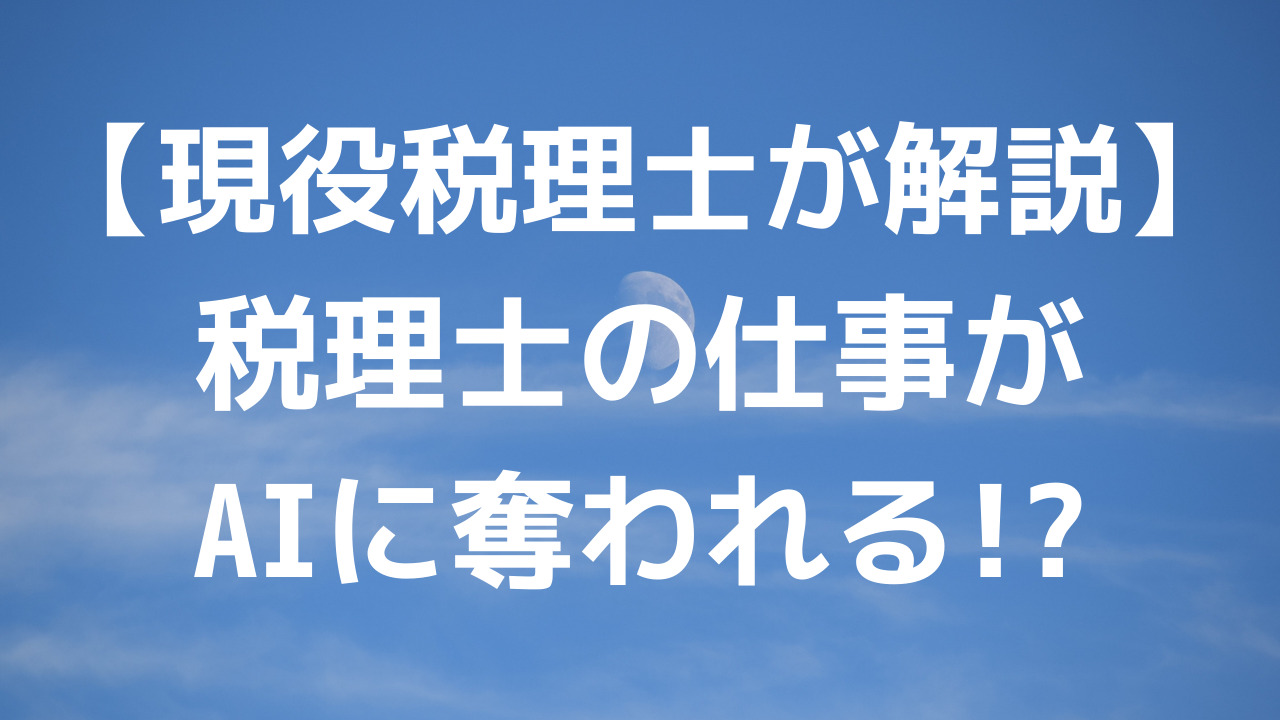
.png)
円満相続税理士法人 税理士
学生時代に税理士試験の受験を始め、在学中に4科目取得し群馬県の会計事務所に就職。売上規模数十億円の企業の法人税、相続税を担当しつつ25歳の時に税理士試験合格。
皆さんこんにちは。
大宮円満相続税理士法人、代表税理士の加藤です。
税理士業界で働いているとこんな話を耳にしませんか?
税理士の仕事は10年後AIによってなくなりますよ!
この話、実は全くありえない話ではありません。(10年後は早い気もしますが笑)税理士でさえ仕事が無くなるかもしれない今、税理士事務所で働いている方の不安も増すばかりです。
その話題について私の意見を簡単に述べると、
10年後、自身の能力を伸ばしていくことが出来ていない税理士や職員の方は厳しくなる可能性が高い!
と思っています!
それではこの時代の税理士業界を生き抜くにはどのようにすればよいでしょう?
今回は今後も税理士業界で活躍できるように、今からやっておく対処法の一つをご紹介します!
もし今を不安に感じている方がいるのであれば、ぜひご覧ください!
相続税の勉強をする
税理士業界で生き抜いていく方法、
それは自分の価値を上げることです!
AIで奪われてしまう仕事は単純作業です。税理士事務所で働いている方たちに求められるものは、より高度なものになっていくでしょう。
そんな中で何も行動を起こさないのは非常にリスクが高く知識と技術を身につけ、周りの人達と差別化を図ることが必要です。
そんなこと分かっているけど…実際何をしたらいいんです?
その答えの一つが相続税の勉強です!
人口減少、少子高齢化に伴い税理士業界の仕事の多くは先細りしていくと思われます。そのような中で今後需要の拡大を見込まれるものが相続税です。
相続税の知識がある人と無い人とでは、どちらが人財として重宝されるのかは火を見るよりも明らかですね!また相続税はお客様の事情が一人一人異なり複雑なので、AIに仕事が奪われる可能性も他のものと比べると低いです。
条文にチャレンジ!
さて、それでは皆さん相続税の勉強を頑張ってください!…と言われてもどのようにすれば良いのか分かりませんよね。
税理士事務所で働いている以上、お客様には正確な情報を提供しなければいけません。
そこで皆さんには条文ベースでの学習をおすすめします!
普通の方であれば税理士事務所や会計事務所がHP等で簡潔にまとめている情報で良いかもしれませんが、皆さんは税金のプロとしてその根拠(つまり条文です!)をしっかりと把握しましょう。
しかし税法条文というものはかなり複雑です…皆さんは税法を読んだことがありますか?
試しに条文をそっくりそのままの状態で読んでみてください(難しくなってきたら読み飛ばしてくださいね)
- 相続税の納税義務者
- 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
- 一 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
- イ 一時居住者でない個人
- ロ 一時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
- 二 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
- イ 日本国籍を有する個人であって次に掲げるもの
- (1) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
- (2) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続又は遺贈に係る被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
- ロ 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
- 三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
- 四 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)
- 五 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前各号に掲げる者を除く。)
いかがでしたか?
すぐに理解できました!
という方は素晴らしいです!私がお力になれることはないでしょう…
一行目からチンプンカンプンですー
という方はご安心ください!これから私が相続税を理解する上で重要な条文を紹介するので一緒に勉強しましょう。
相続税で重要な条文を理解しよう
- 相続税の納税義務者
- 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
- 一 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
- イ 一時居住者でない個人
- ロ 一時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
条文のタイトルは「相続税の納税義務者」と書いてあります。つまりテーマは相続税はそもそも誰が納めるのかということです。
タイトルの次にはこんな文章があります。
次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
「各号」というのはこの文章以降に出てくる「一」や「二」という数字です。この文によれば、これから説明される人たちは相続税を納めなければいけないということが分かりますね。
さて、それではどのような人たちが該当するのでしょうか?
一 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であって
頭に「一」という数字がありますが、この条文ではこれが「五」まで続きます。(今回は「一のみ抜粋しています。)
相続税を納める人が5種類もいるんですか…
遺贈とは?
1種類目を見ていきます!
「相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であって」
「相続」は皆さんが思う相続で問題ないですね!次の「遺贈」はどうでしょう?
「遺贈」とは遺言で財産を贈ることで、基本的には相続によって財産を引き継ぐ場合と同じく取り扱います。ただし遺贈は相続と異なり、誰でも好きな人に自分の財産を残せます!
やったー!友達にも財産を残せるんですね!
その通りです!実務では遺贈を用いることも多々ありますので、気になる方はとても面白いので勉強してみてください!
贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与!?
その遺贈の次のカッコ書きの「(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)」とはどのような意味でしょう?
亡くなったのに贈与するんですか!?
贈与というものは通常生きている人が、他の生きている人に自分の持っているものを渡す行為をいいますが「贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与」という文言が複雑にしていますね…
この文言の考え方はこのようになります。
私が死んだら先祖代々受け継いできた指輪を娘のあなたにあげちゃうよん!
本当に?ありがとうお母さんっ!!
さてこの場合、贈与という行為が行われるのはいつでしょうか?
お母さんが亡くなったときじゃないでしょうか!?
完璧です!これが先ほどの「贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与」となります。ちなみにこのような贈与の方法を「死因贈与」といいます。
つまり「死因贈与」で財産をもらった人も相続税(贈与税ではありません!)を納めなければならないよ、ということですね。
また「以下同じ」という言葉があるため、この条文の中では「遺贈」とあればその中には必ず「死因贈与」も含まれることになります。
結局納税義務者って?
ここまでを整理しましょう。
ある人が亡くなりその人の持っていた財産が他の人のところに移っていきます。何があったでしょうか?
相続・遺贈・死因贈与の3つです!
その通りです!
「相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であって」
これらで財産を取得した人のことを回りくどい言い方で表現しています。
うーん…でも、次に掲げる者ってなんですか?
いいところに気付きましたね!気になるところもあると思いますが、少しお待ちいただいて次の文を先に見ていきましょう!
当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
この文章で分かりづらいところは「この法律の施行地」という言い回しだと思います。
「この法律」とは相続税法のことですね。
「施行」とは法律を実施することをいいますが、「この法律の施行地」とは簡単に言ってしまえば「日本」です。
つまり前述した理由で財産をもらった時に日本に住んでいた人ということです。
亡くなった人から3つの方法で財産をもらって、そのときに日本に住んでいたから相続税を納める義務があるってことですか?!
と言いたいところですが、もう一つ条件があります。それが先ほどの「次に掲げる者」です!次に掲げる者とは、
イ 一時居住者でない個人
ロ 一時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
この部分に書いてあります。ここでは三つの重要な単語が登場します。
「一時居住者」「一時居住被相続人」「非居住被相続人」です。
ただこの内容はやや複雑な面があります。
財産をもらった人か亡くなった人のどちらかがずっと日本に住んでいた時は「イ」に当てはまるので、今のところはこんな人達がいるんだなー程度にとどめておいて大丈夫です!
では最後に今までの事項をまとめましょう。
今回は相続税を納めなければならない5種類の人のうちの1つ目でした。その要件は何でしょうか?
相続・遺贈・死因贈与で財産をもらいました!
財産をもらった人が日本に住んでいます!
財産を貰った人か、亡くなった人がずっと日本に住んでいます!
そうですね、この要件を満たすと相続税を納める義務がある人となります。
ちなみにこの1つ目の人を「居住無制限納税義務者」と呼ぶので覚えておきましょう。
まとめ
ここまで終えてみていかがでしたか?
条文なんて読み慣れていないから疲れました…
確かに読み慣れない条文は疲れますよね。
しかしながら誰でも簡単に得ることの出来る知識で、他の人達と差別化を図り、お客様や会社から重宝される人財になれるでしょうか?
答えはNOです!他の人達では分からないことを知っている、これが差別化につながります。
初めから100%の力で取り組んでも、途中でエネルギーが切れてしまうので、ゆっくり無理のないペースが第一です。少しずつでも、のんびりでも構いませんので努力は継続することが大切です。
この勉強はあくまでも仕事をする上での基礎となる情報ですので、より実務的なこと等は弊社が発信しているメルマガや、円満相続塾で提供しておりますので是非参考にしてください!