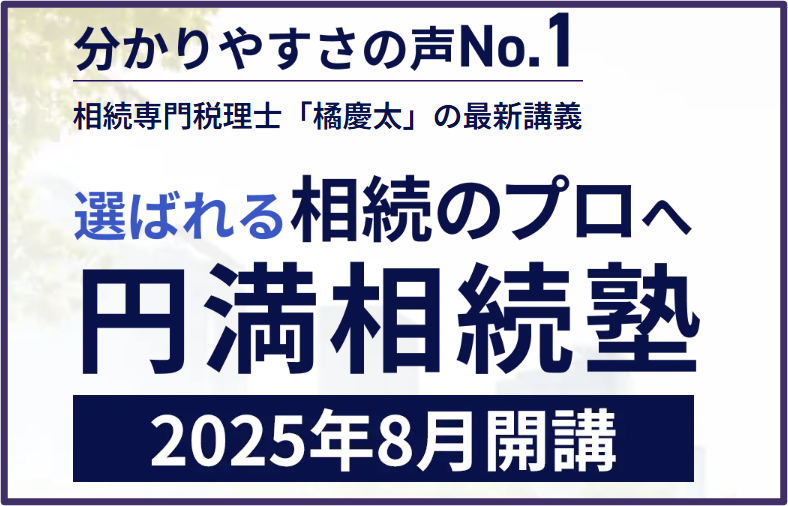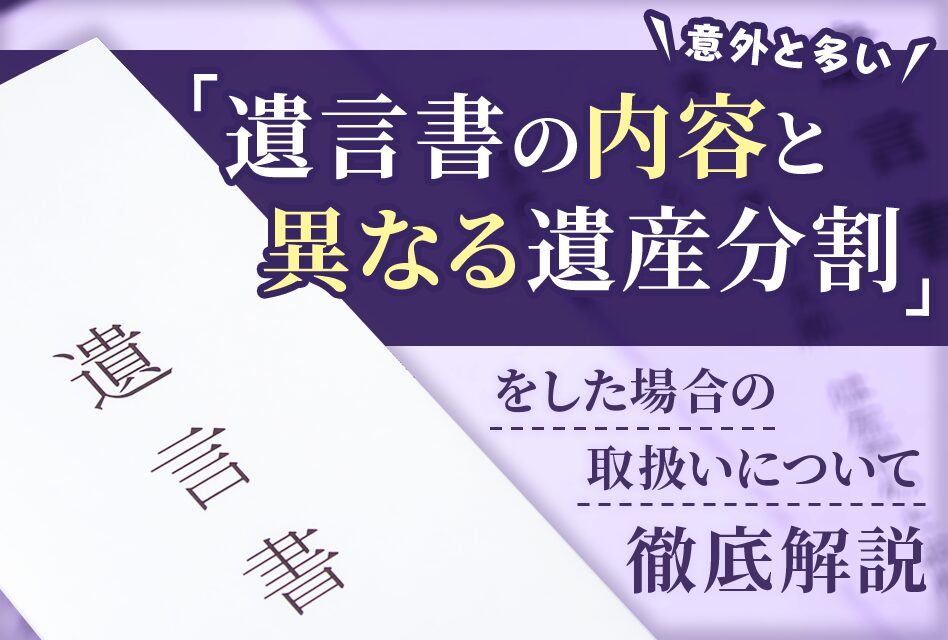

円満相続税理士法人 税理士
大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!
こんにちは!税理士の枡塚です。
遺言書がある場合には、原則、その遺言書に沿って遺産を承継しますが、実務上、遺言書とは異なる内容で遺産を承継したいとご希望されるご家族は意外と多いです。
遺言書は故人の想いと理解しつつも、ご相続人皆様の現在の生活状況や今後のご家族関係を考慮して、そのように希望されるご家族は多いですが、税務上、問題はないのでしょうか?ここでは、遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の税務上の取扱いについて、解説していきます!
遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことは可能か?
被相続人である父は、「全財産を長男Aに相続させる」の遺言を残して亡くなりました。
長男Aの他に、相続人は長女B、次女Cですが、長男Aは兄妹平等に相続したいと考えています。
長男Aの考えは実現可能でしょうか?
このような相続させる旨の遺言を『特定財産承継遺言』といいますが、次のように判示されているため、遺言書と異なる遺産分割を行うことはできないという見解を持つ方もいるかもしれません。
最高裁判決平成3年4月19日
相続させる趣旨の遺言は、正に同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このような遺言にあっては、遺言書の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続による承継されるものと解するべきである
一方、この最高裁判決について、地裁レベルではありますが、全ての相続人が納得して、円満に相続できるのであれば、遺言とは別の内容で遺産分割を行うことも認められるべきと判示し、実務上もこの取扱いが用いられています。
さいたま地裁平成14年2月7日
『特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がなされた場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該不動産は当該相続人に相続により承継される。そのような遺言がなされた場合の遺産分割の協議又は審判においては、当該遺産の承継を参酌して残余の遺産の分割がされることはいうまでもないとしても、当該遺産については、上記の協議又は審判を経る余地はない。以上が判例の趣旨である(最判平成3年4月19日第2小法廷判決・民集45巻4号477頁参照)。しかしながら、このような遺言をする被相続人(遺言者)の通常の意思は、相続をめぐって相続人間に無用な紛争が生ずることを避けることにあるから、これと異なる内容の遺産分割が全相続人によって協議されたとしても、直ちに被相続人の意思に反するとはいえない。被相続人が遺言でこれと異なる遺産分割を禁じている等の事情があれば格別、そうでなければ、被相続人による拘束を全相続人にまで及ぼす必要はなく、むしろ全相続人の意思が一致するなら、遺産を承継する当事者たる相続人間の意思を尊重することが妥当である。法的には、一旦は遺言内容に沿った遺産の帰属が決まるものではあるが、このような遺産分割は、相続人間における当該遺産の贈与や交換を含む混合契約と解することが可能であるし、その効果についても通常の遺産分割と同様の取扱いを認めることが実態に即して簡明である。また従前から遺言があっても、全相続人によってこれと異なる遺産分割協議は実際に多く行われていたのであり、ただ事案によって遺産分割協議が難航している実状もあることから、前記判例は、その迅速で妥当な紛争解決を図るという趣旨から、これを不要としたのであって、相続人間において、遺言と異なる遺産分割をすることが一切できず、その遺産分割を無効とする趣旨まで包含していると解することはできないというべきである。
まとめると、以下の条件を満たしている場合には、遺言書と異なる遺産分割をすることが可能というわけです。
遺言書の内容を知った上で相続人全員がその内容と異なる遺産分割を行うことに同意していること
相続人以外に受遺者がいる場合には、その受遺者全員が同意していること
遺言書に遺産分割協議を禁止する文言がないこと
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意を得ていること
税務上の取扱い
まさに、遺言の内容と異なる遺産分割をしたときの相続税と贈与税の取扱いが、国税庁ホームページのタックスアンサー(NO.4176)に掲載されています。
それによると、事実上遺贈を放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当であり、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。
つまり、受遺者である相続人に一旦相続税が課税された後に、他の相続人対して贈与があったと解して贈与税を課する等の特別な課税関係は生じず、遺産分割協議を基に相続税を計算すれば良いということです。
もっとも、特定財産承継遺言に従って相続税申告や登記・名義変更が完了してしまっていると、相続による財産承継の効果が確定してしまっているとみられます。その後、遺言と異なる内容の遺産分割をした場合には、たとえ上記の条件を全て満たしていても、それはもはや遺産分割ではなく、『贈与』や『交換』と解され、贈与税や所得税が課税されることになるため、注意が必要です。
まとめ
遺言があるからといって、その通りに財産を承継しないといけないというわけではありません。故人の想いを残しつつ、生活の状況や税金のことも考え、より最適な遺産分割方法がないか、検討してみましょう。