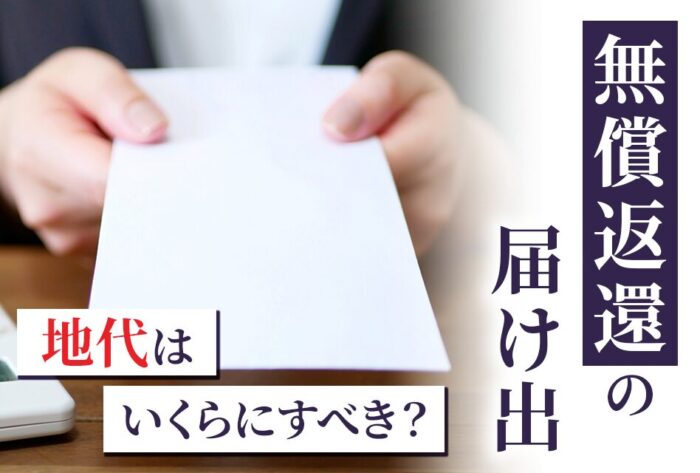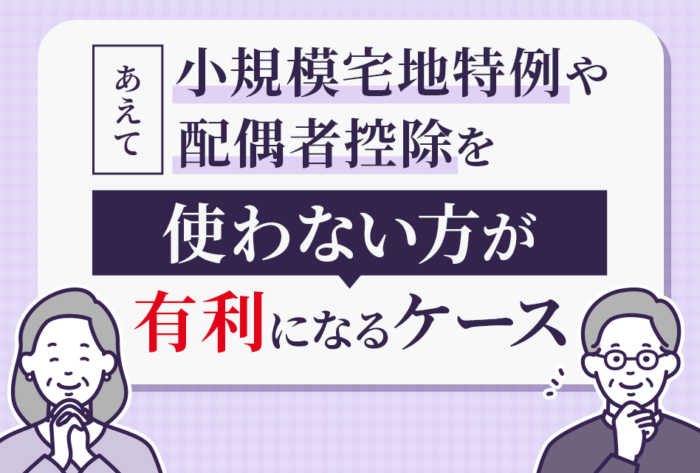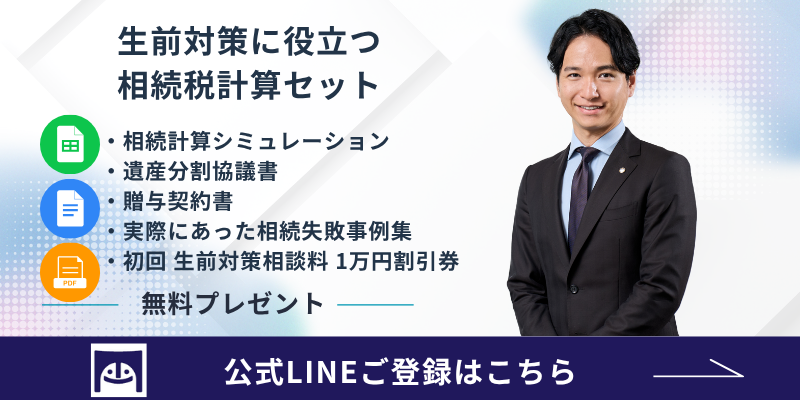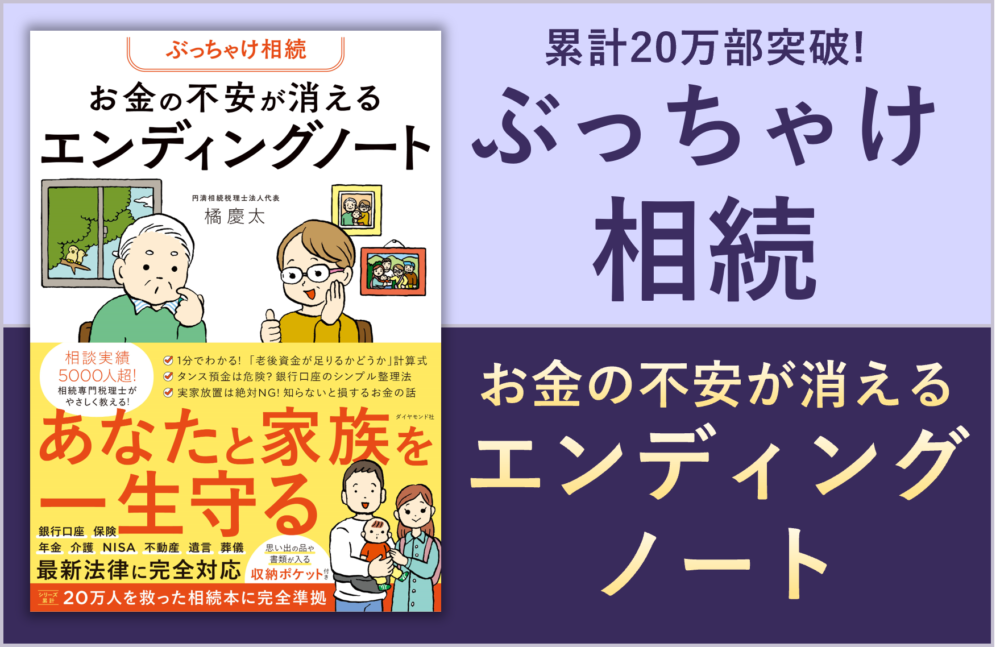円満相続税理士法人 公認会計士・税理士
在学中に公認会計士試験に合格し、監査法人、コンサル、公務員を経て、円満相続税理士法人へ入社。相続・事業承継のプロとしてご家族のサポートができるよう業務に携わっています!
事業承継税制を使う際に、万が一、将来打ち切り事由に該当し、多額の贈与税を支払うことになるリスクに備え、相続時精算課税を選択することがあります。
従来は、事業承継税制と相続時精算課税は併用することができませんでしたが、平成29年度税制改正で、併用が可能となりました。
さらに、平成30年度税制改正で設けられた、特例措置においても、もちろん併用可能です。事業承継税制の特例については、こちらの動画で詳しく解説しています。
今回は、事業承継税制と相続時精算課税の併用について、解説していきます。
相続時精算課税のおさらい
ここで、相続時精算課税について、おさらいしておくと、適用要件は、以下のとおりです。(相続税法第29条の9第1項、孫は租税特別措置法第70条の2の6第1項)
贈与者が、60歳以上
受贈者が、直系卑属の推定相続人または孫で、18歳以上
そして、相続時精算課税の注意点は以下の2つです。
自動継続(相続税法第29条の9第3項)
取消不可(相続税法第29条の9第6項)
なお、令和6年以降は、年間110万円以下の贈与なら、相続時精算課税を選択した後でも、その年分の申告は不要です。
<相続税法>
(相続時精算課税の選択)
第二十一条の九 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において十八歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第二十八条第一項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
4 その年一月一日において十八歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき(配偶者となつたときを除く。)には、推定相続人となつた時前にその者からの贈与により取得した財産については、第一項の規定の適用はないものとする。
5 第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第三項の規定の適用があるものとする。
6 相続時精算課税適用者は、第二項の届出書を撤回することができない。
<租税特別措置法>
(相続時精算課税適用者の特例)
第七十条の二の六 平成二十七年一月一日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫(その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与をした者がその年一月一日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
特例措置では子や孫でなくても併用可能
さらに、事業承継税制の特例措置では、直系卑属の推定相続人または孫でなくても、先代経営者から後継者への贈与について、相続時精算課税を使うことができます。
租税特別措置法第70条の2の8で準用する、同法第70条の2の7第1項において、特例経営承継受贈者が、贈与者の直系卑属の推定相続人または孫以外の者である場合について、相続税法第21条の9(相続時精算課税の規定)を準用することとされています。
ここで注意しなければならないのは、以下の3点です。
事業承継税制に係る贈与より前に贈与された財産には相続時精算課税の適用はない(租税特別措置法第70条の2の8で準用する、第70条の2の7第2項)
→逆に言うと、事業承継税制に係る贈与以後に贈与された財産には相続時精算課税が適用される
納税猶予の打ち切りや免除があっても、相続時精算課税が継続する(同条第3項)
本来の相続時精算課税を適用した者と同様に、その他の関係規定が適用される(同条第4項)
つまり、子や孫以外の後継者に事業承継税制の特例措置を使って、株式を贈与する際に、相続時精算課税を選択した場合には、それ以降の贈与は相続時精算課税が適用されるし、その後の取り消しもできないということです!
子や孫に相続時精算課税を使った場合と同じということですね。
ちなみに、子や孫以外の後継者が相続時精算課税を使う場合には、事業承継税制を使うことが前提となるので、相続時精算課税の特別控除により納税猶予額がゼロとなる場合は、事業承継税制の適用がありませんので、相続時精算課税の選択ができません。
(もちろん、暦年課税で、事業承継税制を使うことはできます。)
<租税特別措置法>
第七十条の二の七 贈与により第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)を取得した同条第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者(同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者をいう。以下この条において同じ。)が贈与者(その贈与をした第七十条の六の八第一項に規定する贈与者をいう。以下この条において同じ。)の直系卑属である推定相続人以外の者(その贈与者の孫を除き、その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により当該特例受贈事業用資産を取得した特例事業受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
2 特例事業受贈者が贈与者(その年一月一日において六十歳以上の者に限る。)からの贈与により特例受贈事業用資産を取得した場合において、当該特例受贈事業用資産の取得の時前に当該贈与者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
3 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した特例事業受贈者が、第七十条の六の八第四項に規定する猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定した場合又は免除された場合においても、贈与者からの贈与により取得した財産については、第一項において準用する同法第二十一条の九第三項の規定の適用があるものとする。
4 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した特例事業受贈者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、贈与者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の二の八 前条の規定は、贈与により第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者(その贈与をした同条第一項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。)の直系卑属である推定相続人以外の者(その特例贈与者の孫を除き、その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)であり、かつ、その特例贈与者が同日において六十歳以上の者である場合について準用する。
相続時精算課税が不利になるケース
以下の2つのケースでは、事業承継税制と相続時精算課税を併用した場合に、暦年課税より税務上不利になる可能性があります。
先代経営者が相続税の限界税率が高い方で、納税猶予の打ち切りになった場合
事業の継続が困難な事由による免除を受ける場合
先代経営者が相続税の限界税率が高い方で、納税猶予の打ち切りになった場合
具体的な事例で見ていきたいと思います。
株価1億円の株式を事業承継税制を使って贈与したが、打ち切り事由に該当してしまった場合で、先代経営者の相続税の限界税率が55%の場合を考えます。
暦年課税ですと、一般税率を適用しても、(1億円-110万円)×55%-400万円=5,039.5万円の贈与税額の支払いとなります。
相続時精算課税ですと、(1億円-2,500万円)×20%=1,500万円の贈与税額の支払いが生じます。
そして、先代経営者が亡くなった際に、1億円×55%(限界税率)-1,500万円(贈与税額)=4,000万円の相続税額が増加し、先に支払った贈与税額と合わせて、5,500万円となり、暦年課税より460.5万円多くなります。
ただし、実際の有利不利の判定には、打ち切り事由に該当した際に支払う利子税も考慮する必要があります。
事業の継続が困難な事由による免除を受ける場合
事業の継続が困難な事由による免除は、詳細な説明は割愛しますが、事業の継続が困難な事由が生じたことにより対象株式を譲渡した場合には、その時の価額で贈与税を再計算できるというもので、本来払うべき贈与税額と再計算した贈与税額との差額が免除されます。
暦年課税ですと、免除されない部分に対する贈与税を納めて課税関係は完結しますが、相続時精算課税を選択していると、先代経営者が亡くなった際に、免除されない部分を相続財産に持ち戻して相続税を計算しなければなりませんので、1つ目と同じく相続税の限界税率が高い方だと不利になるケースがあります。
先代経営者よりも後継者の方が先に亡くなってしまった場合
最後に、先代経営者よりも後継者の方が先に亡くなってしまった場合ですが、猶予されていた贈与税が免除されて、課税関係は完結します。(もちろん、後継者が所有している株式は、後継者を被相続人とする相続税の対象になります。)
相続時精算課税を選択していた場合、通常は、先代経営者が亡くなった際に、相続財産に持ち戻して相続税を計算し、相続時精算課税による納税に係る権利及び義務は、先に亡くなった後継者の法定相続人が承継しますが、事業承継税制を適用していた場合は免除された部分は持ち戻さなくてよいので、結果的に持ち戻すものは無く、暦年課税でも相続時精算課税でも有利不利は生じないこととなります。
<租税特別措置法第七十条の七第十三項>
九 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が第十五項、第十六項又は第二十一項の規定により猶予中贈与税額の全部又は一部の免除を受けた場合において、第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等(相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)の贈与者の相続が開始したときは、当該対象受贈非上場株式等のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。
まとめ
事業承継税制と相続時精算課税の併用について、解説しました。
相続時精算課税を選択した場合に不利になるケースがゼロではないものの、万が一、打ち切り事由に該当してしまった場合の多額の贈与税の支払いという観点でいうと、やはり相続時精算課税の選択がオススメできるのではないかと考えられます。
(上述の事例でも、贈与税だけで見ると、5,039.5万円と1,500万円という大きな差異がありました。)
私たち、円満相続税理士法人では、事業承継のご相談を行っていますので、こちらもご覧ください。