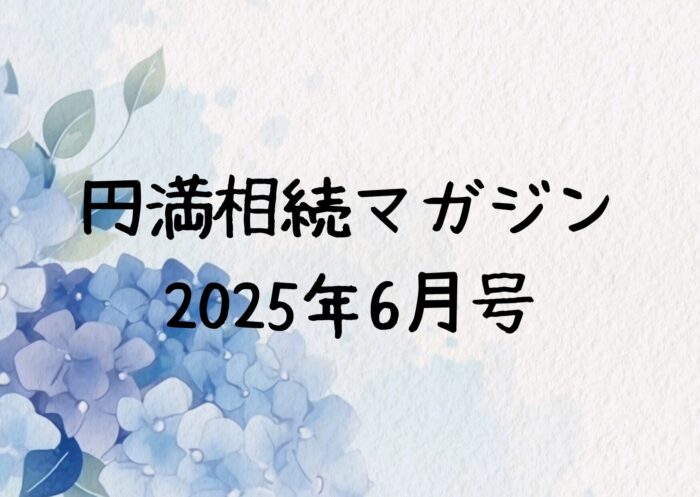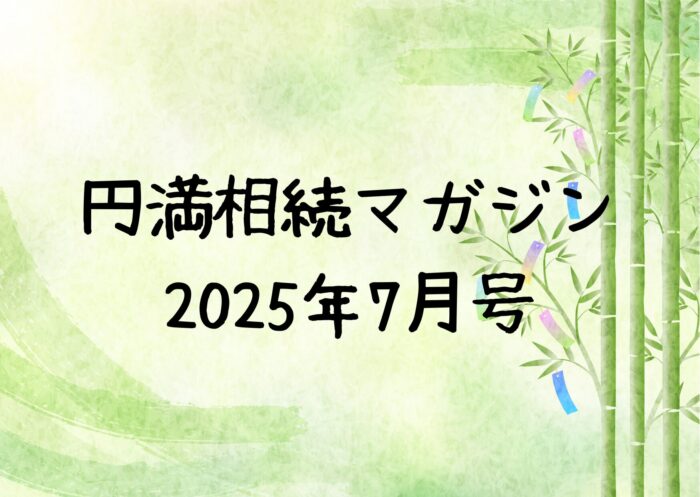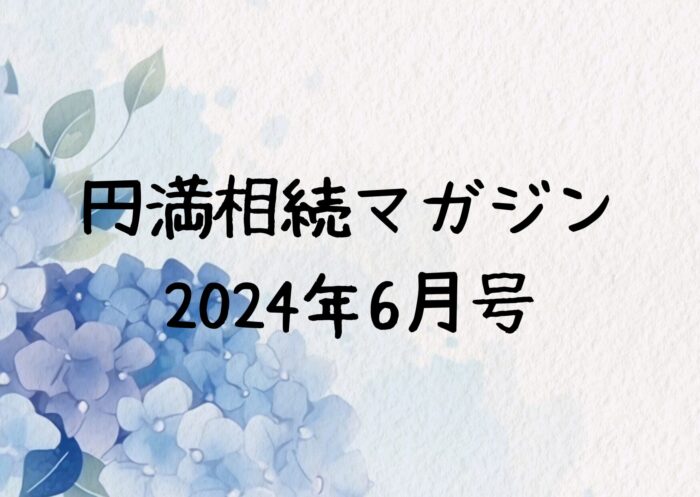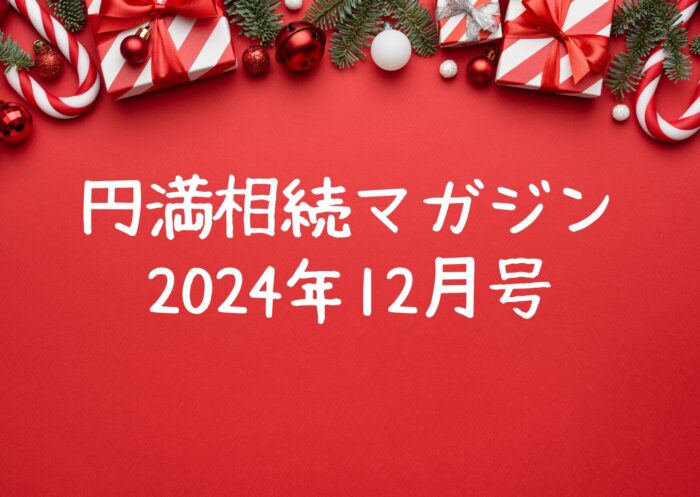今月のニュース
暑気払いでBBQを行いました!
東京事務所の野本です。
弊社では年に2回、新年会と暑気払いにて全拠点(東京、大宮、大阪、名古屋)のメンバーが集まり、ご家族も参加できる機会を設けております。
先日、その暑気払いをキラナガーデン豊洲にてBBQを行いました!!
食材は施設の方が用意してくださり手ぶらでBBQが楽しめる場所となっております!
お肉は3種類、海鮮、野菜と盛りだくさんで大満足!
キッズプレートもありましたので、お子様連れのメンバーも一緒に楽しめました。
他拠点の皆さんとは久しぶりにお会いしたのと新たなメンバーも多くいたので、
予約した4時間があっという間に過ぎていきました。。。
もうすでに来年の新年会が楽しみです!
また、間もなく弊社が創立10周年を迎えるので、社員旅行も企画する予定です!
たくさん楽しいイベントを開催できるように日々の業務に邁進していこうと思います!
これから夏本番ですので、皆さま熱中症等には気をつけてお過ごしください!

夏季休業期間のお知らせ
2025年8月13日水曜日から8月17日日曜日まで夏季休業期間とさせていただいております。
誠に恐れ入りますが、この期間でのお問合せは、8月18日月曜日、午前9時以降に、順次対応いたします。
相続時精算課税と暦年課税の選択はどのように考えるべきか【税のトピック1】
名古屋事務所の土屋です。今回は、贈与税の制度、相続時精算課税と暦年課税のどちらを選択すれば良いのか、具体例で考えていきたいと思います。
生前贈与で相続時精算課税と暦年課税のどちらを選択すべきですか?
具体例
まず、前提ですが、相談者さんの家族構成は次のとおりとします。
・お父様(88歳)とお母様(80歳)がご健在です。
・お父様とお母様には子供1人(相談者さん)がいます。
・お父様の財産は総額2億円です。
・お母様の財産は総額1000万円です。
平均余命で想定してみる
お父様の財産は相続税の基礎控除を超えているので相続税の申告が必要になります。生前にお父様とお母様の両方から贈与してもらうことで相続税の節税につながります。
そこでお父様とお母様があと何年生きるのかを想定します。
想定すると言っても、人間の寿命は当の本人でもわかりませんので、とりあえず「平均余命」で亡くなるものとします。
平均余命は厚生労働省が公表している「簡易生命表」を参考にします。
すると、お父様(88歳男性)は4年後に、お母様(82歳女性)は10年後に亡くなるのではないかと想定されます。
お父様は相続時精算課税で!
お父様があと4年で亡くなるとするなら、暦年課税の場合、お父様からの贈与を年間110万円以内に抑えると贈与金額110万円-基礎控除110万円=0円で贈与税は課税されませんが、440万円(贈与金額110万円×4年分)が相続税において相続開始前7年以内贈与加算されるため節税になりません。
相続開始前7年以内の贈与は、暦年課税の場合、たとえ110万円以内に抑えていても結局、相続税に加算されてしまうのです。
(注意:相続開始前7年以内贈与加算は令和6年1月1日以降の贈与に適用されますが、当ブログ掲載時点では実質的にはまだ3年以内贈与加算です。今後、段階的に7年以内贈与加算に移行されます。)
そこで、お父様からの贈与については相続時精算課税を選択します。
相続時精算課税であればお父様からの贈与を年間110万円以内に抑えれば、毎年110万円の基礎控除を適用できますので、相続税において加算される生前贈与の金額は0円です。
相続時精算課税だと年間110万円以内の贈与なら相続税に加算されないのです。
ここが暦年課税との大きな違いとなっています。結論として、相続が7年以内と想定されるお父様からの贈与は暦年課税ではなく、相続時精算課税を選択すべきということになります。
お母様は最初は暦年課税、次に相続時精算課税で!
一方、お母様からの贈与はどう考えるべきでしょうか。
母は財産が1000万円しかないから相続税は関係ないよ。
確かに1000万円なら相続税の基礎控除以下ですね。しかし、お父様が先に亡くなることにより、お母様はお父様の遺産2億円のうち、いくらかを相続することになります。
例えば、2億円のうち1億円を相続すると相続税は配偶者税額軽減を適用して0円になりますが、お母様の財産はもともと持っていた1000万円に相続財産1億円が加わりますので1億1000万円となり、お母様がお亡くなりになった際に相続税の申告義務が生じることになります。
お母様についても生前贈与してもらうことが有効な相続税対策になります。
では、お母様からの贈与は暦年課税か相続時精算課税かどちらを選択すべきでしょうか。
母は平均余命で計算すると、あと10年生きることになるから、今から最初の3年間は暦年課税で生前贈与して、4年目からは10年目の7年間は相続時精算課税に切り替えるのがいいのでは?
正解です。想定どおり10年目でお亡くなりになるならその選択になりますね。
最初の3年間は暦年課税で110万円の基礎控除により贈与税を回避しつつ、相続税にも加算されません。
4年目~10年目は相続時精算課税に切り替えることで年間110万円を贈与税にも相続税にも加算されなくなります。
ただ、先にもお話したように人の寿命は分かりません。
お母様は82歳ですので、いつお亡くなりになるかわかりません。
お母さまについても念のため1年目から相続時精算課税とするのもアリですがその場合、注意点があります。
それは、相続時精算課税の基礎控除110万円はお父様とお母様の合計で110万円しか適用できないことです。
同じ年にお父様とお母様の両方から相続時精算課税で生前贈与を受けると、お父様からの贈与に55万円しか基礎控除を適用できず、お母様からの贈与にも55万円しか基礎控除を適用できなくなります(次の計算になります)。
・お父様からの贈与額110万円-基礎控除55万円=相続税に加算されてしまう金額55万円
・お母様からの贈与額110万円-基礎控除55万円=相続税に加算されてしまう金額55万円
つまり、相続税の計算に加算されてしまう生前贈与55万円が発生してしまうことにより節税効果が小さくなってしまいます。
まとめ
以上、具体例で相続時精算課税と暦年課税の選択を解説しました。
基本的な考え方は余命があと7年以内と想定される場合は相続時精算課税を選択するということです。
繰り返しますが、人の寿命は本人でさえ分からない不確実なことですから、相続時精算課税と暦年課税の選択は想定どおりにならないことも受容して決定していきたいところです。
また、今回は年間の贈与額は110万円以内という前提でしたが、これは生前贈与の一例に過ぎません。
あえて110万円以上の贈与をして贈与税を支払うことで相続税の節税になるという手法もあります。
様々な節税手法がある中で、ご自分に合った最適な選択をするには相続が始まる前に相続専門税理士に相談されることをお勧めします。
お墓は生前に建てるとお得?終活で節税【税のトピック2】
こんにちは、東京事務所の税理士 鈴木です。
多くの人にとって「お墓を建てる」というのは人生で一度あるかないかの大きな決断です。
近年では、「終活」の一環として生前にお墓を建てる人が増えています。
これは気持ちの整理だけではなく、相続税の節税という面でもお得な選択となることをご存じでしょうか?
相続税と「お墓」の関係
相続税は、亡くなった方の財産を相続人が受け継ぐ際に課される税金です。
しかし、お墓・仏壇・仏具・神棚・十字架などの「祭祀(さいし)に関する財産」は、法律上、非課税財産として扱われ相続税がかかりません。
これは、これらの財産が金銭的価値よりも、先祖供養という精神的・文化的な意義を重視しているためです。
祭祀財産とは?
祭祀(さいし)とは、祖先や神をまつる行為のことをいいます。
そして祭祀財産とは、系譜(けいふ)、祭具(さいぐ)、墳墓(ふんぼ)といった、祖先や神をまつるために必要な財産のことをいいます。(民法897条)
・系譜:いわゆる家系図や家系譜です。
・祭具:仏具・位牌・神棚・十字架など祭祀に用いられる器具のことです。
・墳墓:いわゆるお墓です。
これらは、「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」として、相続税の非課税財産となっています。(相続税法12条1項2号)
生前にお墓を建てるメリット
・節税につながる
たとえば、生前に現金150万円でお墓を購入した場合、そのお墓は非課税財産のため、相続税がかかりません。
一方、亡くなった後に相続人が150万円の相続財産からお墓を建てると、その現金は課税対象になります。
生前に必要な購入しておくことで、相続税の圧縮につながります。
・家族の負担を軽減できる
霊園探し・墓石選び・業者との打ち合わせなどは、遺族にとって少なくない負担です。
生前に準備することで、遺された家族が精神的・経済的に楽になるでしょう。
・自分の希望を反映できる
「こんなお墓がいい」「この場所がいい」といった希望を、自分自身で形にできるのも大きなメリットです。
お墓参りの利便性や維持費も考慮して、ご家族にも相談しておくと安心です。
生前にお墓を建てる注意点
・高額すぎる祭祀財産は相続対策にならない
財産に対してあまりにも高額すぎるお墓や、宝石装飾が施された墓石、純金製の仏具などは贅沢品とみなされ、相続税がかかる可能性があります。
国税庁のタックスアンサー「相続税がかからない財産」にも、「ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。」と記載があります。
相続税が非課税となるのは、本当に祖先供養に使うものに限られますのでご注意ください。
・お墓を購入するためのローンは債務控除不可
通常、債務は相続税の計算において財産から差し引いて相続税を計算しますが、お墓が非課税財産であることから、非課税財産(お墓)を購入するためのローンも相続税の計算から除外されます。
相続対策であれば、余剰現金で購入するようにしましょう。
・お墓には管理費がかかる
購入後は霊園や寺院の管理費が発生するため、長期的な維持も見据えて計画を立てることが大切です。
まとめ:お墓の準備は「相続対策」のひとつ
お墓を生前に建てることは、人生の終盤を整える“終活”としての意味合いだけでなく、相続税の節税にも有効です。
お盆などご家族が集まる機会に、お墓やご相続について前向きに話し合ってみてはいかがでしょうか。
具体的な相続対策や相続税の試算については、お気軽に円満相続税理士法人にご相談ください。
円満相続塾2025年8月開講
円満相続塾、既に多くの方からエントリーをお受けしています♪
相続のプロフェッショナルを目指す方に向けて、相続を網羅的に伝える円満相続塾を2年ぶりに開講します!日程は下記の通りです。8月からの3ヶ月間で、相続に強いプロフェッショナルに成長していきましょう。
8月23日(土)~11月8日(土)までの毎週土曜(12回)、15時~18時30分までです。
現段階では、税理士さんの参加が最も多く、次に税理士事務所職員さん。
そのあとに、行政書士さん、司法書士さん、生命保険会社の方々が続きます。
相続未経験の方も多くいらっしゃいます。一緒に成長していきましょう(^^)/
編集後記(橘の日常)
YouTube円満相続ちゃんねるが変わります!
今月より、YouTubeちゃんねるの運営方針を変えます。
これまでは、私(橘)が一人で動画制作していましたが、これからは、円満相続税理士法人の全社員でチームを組んで動画更新をしていくことにしました。そのため、私以外のメンバーも、どんどん出演させていきます。
というのも、実はここ数年、目の前の仕事に追われ、動画配信を継続することが中々できていませんでした…。YouTubeを始めたころは、まだお客様も少なかったので、お客様面談の合間に撮影や編集をすることができたのですが、最近は大変ありがたいことにお客様も増え、仲間も増え、日々忙しくさせていただいてます。
この仕事が落ち着いたら、YouTubeやろう…
と思いつつも、一つの仕事が終わったら、また別の仕事が…。
このままじゃいけない!と思い、私一人でやろうとせず、チームを組み、期限を設けてやっていこうと考えました。これなら、続けていける気がします。
具体的には、社内に、企画部、撮影部、編集部、配信部、出演部という5つの部門を作りました。
これまでは、私が一人で淡々と相続税を解説する動画をあげてきましたが、これからは、私ともう一人の税理士が、皆様からいただいた質問や相談を、その場で回答していくQ&Aコーナーなども企画しています(^^)
また、サブチャンネルである税理士試験&就活ちゃんねるでは、私のプライベートVlogや、税理士受験生応援ドキュメンタリー動画なども配信予定です。
何事も継続のコツは、やり続ける強い意志をもつことではなく、やり続けなければいけない環境を創ることだと思っています。自分ひとりの約束から、仲間を巻き込んで約束を共有するのが継続のコツだと思っています(このプロジェクトに快諾してくれている仲間に感謝!)。
というわけで、新しい体制での配信をお楽しみに!
最初の動画は、8月の終わりごろまでには完成させたいな~と思っています。
今月も最後までお読みいただき、ありがとうございました(^^)
橘慶太